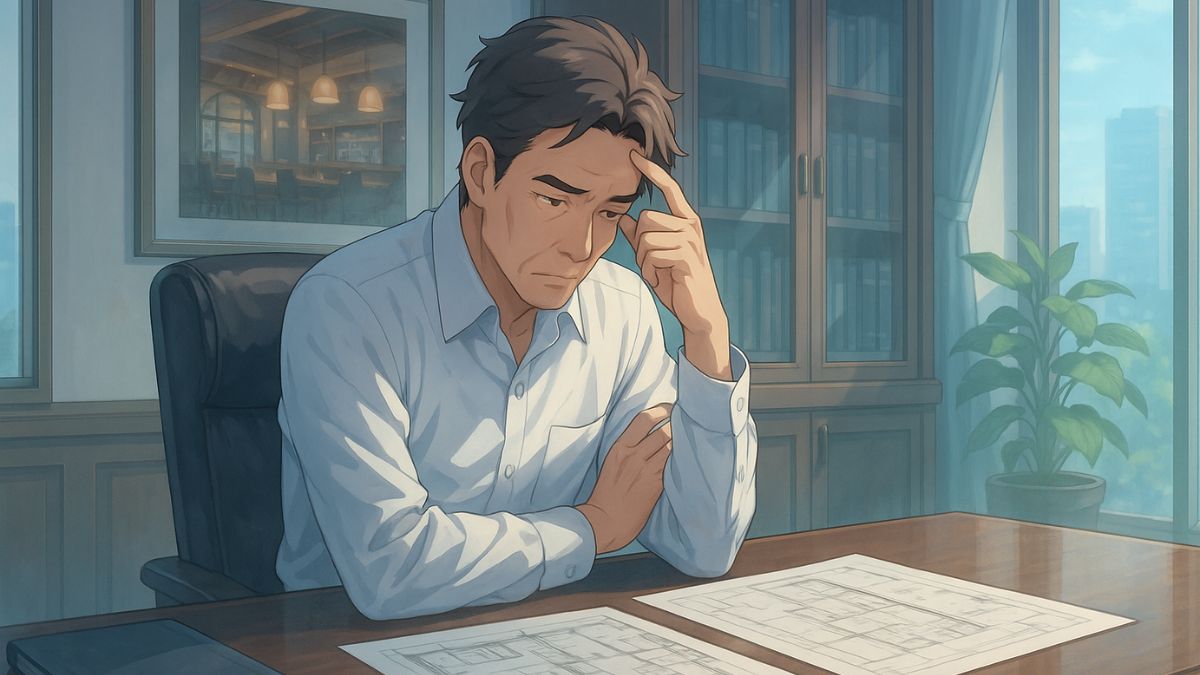台湾での店舗出店において、多くの日本企業が悩むのが「設計施工を一貫で頼むべきか、それとも分離すべきか」という問題です。
一貫方式はスピードと柔軟性に優れ、分離方式は品質と透明性に強い──
どちらにも魅力とリスクがあります。
第1章 設計施工一貫の“スピード感”と“盲点”
― 台湾ではなぜ一貫方式が好まれるのか? ―
台湾で店舗の内装工事を進めると、「設計も施工も、うちで全部やりますよ」という言葉をよく耳にします。
この「設計施工一貫方式」は台湾の内装業界では一般的なスタイルであり、むしろ“分離”のほうが例外にあたります。
日本では、設計は設計事務所、施工は工務店と明確に分けるのが主流ですが、台湾では、ひとつの会社が空間デザインから現場管理、家具製作、サイン設置までをまとめて請け負うことが多いのです。
日本の感覚からすれば、「スピードも早く、コストも抑えられるなら理想的では?」と感じるかもしれません。
しかし、その一方で、
- 「図面が途中で変わった」
- 「仕上がりの品質が不均一」
- 「見積もりに含まれていなかった追加費用が発生した」
などのトラブルも少なくありません。
なぜ台湾では設計施工一貫がここまで浸透しているのか、その背景をひもときつつ、現場のリアルな利点とリスクを考えてみます。
台湾で「設計施工一貫」が主流になった歴史的背景
台湾の内装業界の形成には、日本統治時代の建築文化と戦後のアメリカ的商業文化が複雑に絡み合っています。
戦後の台湾は急速な経済成長とともに、「スピード優先」「現場判断重視」の施工スタイルが定着しました。
特に台北や高雄などの商業都市では、オーナーが「明日には工事を始めたい」「1か月後に開店したい」と求めることが多く、それに応える形で“すぐに動ける”設計施工会社が生まれたのです。
さらに、台湾では中小規模のデザイン会社が多数存在し、それぞれが家具職人や施工チームと独自のネットワークを持っています。
この「横のつながり文化」こそが、一貫方式の発展を後押ししました。
つまり、台湾では「設計会社が現場をまとめる」というより、「施工会社が設計もやってしまう」ケースが多いのです。
それが、台湾における“設計施工一貫”のリアルな出発点といえるでしょう。
スピード重視の市場構造とオーナー志向の関係
台湾の店舗出店では、「とにかく早くオープンしたい」という要望が非常に強い傾向にあります。
これは、賃貸契約が日本より短期で、家賃も高額であることが背景にあります。
1か月でもオープンが遅れれば、それだけで数十万円の損失が出るため、オーナーは“スピード”を最優先に判断するのです。
設計施工一貫方式は、打ち合わせから施工までのリードタイムを圧倒的に短縮できます。
設計担当と施工担当が同じチームで動くため、図面変更も即日対応が可能です。
日本のように「設計変更には再見積もり、承認、再発注」という流れを踏むことなく、現場で即断即決ができるのが台湾流の強みです。
しかし、そのスピードが裏目に出ることもあります。
デザインの細部や仕上げの品質よりも「間に合わせる」ことを優先してしまうため、完成後に「もう少し丁寧に仕上げてほしかった」と感じるケースが少なくありません。
つまり、スピードの裏に、クオリティへの“トレードオフ”があるのです。
設計と現場が近いからこそ生まれる“柔軟対応力”
設計施工一貫の最大の魅力は、現場での柔軟な対応力にあります。
例えば、実際の施工中に「この壁をもう少し前に出したい」「このカウンターの高さを変更したい」といった要望が出たとき、日本なら変更申請と図面修正に時間がかかりますが、台湾では担当者がその場で判断し、即座に職人に指示を出せます。
このスピード感は、特に飲食店や美容室などのオーナー主導型店舗に向いています。
オーナー自身が現場でアイデアを出し、デザイナーと職人がその場で形にしていく──
台湾ではこれが自然な流れです。
日本的な「図面通りに施工する」文化とは違い、「現場で創る」ことを前提にした文化なのです。
ただし、この“柔軟さ”が行きすぎると、「どこまでが設計意図なのか」が曖昧になります。
特に、日本企業が依頼主の場合、「当初のコンセプトと違う」「ブランド基準を満たしていない」といった齟齬が生まれることもあります。
柔軟対応力は魅力ですが、それを制御できる“監理者的存在”が必要なのです。
設計変更が容易な反面、品質基準が曖昧になりやすい理由
台湾では、内装図面が「最終図面」にならないことがよくあります。
現場で変更が加えられることが前提のため、設計段階でのディテール図が十分に整っていないまま工事が進むケースが多いのです。
たとえば、仕上げの面材の貼り方向、照明の配置ピッチ、巾木の納まり──
日本なら必ず図面に明記される部分が、台湾では“現場判断”に委ねられることも珍しくありません。
こうした状況が生まれる理由は、台湾の設計施工会社における「監理者」という役職の希薄さです。
日本では、設計者が現場に足を運び、図面通りに進んでいるかを確認しますが、台湾では設計担当が現場に常駐することは稀です。
そのため、現場側が「このほうが早い」「この材料のほうが入手しやすい」と判断し、独自に仕様を変更してしまうことが起こりやすいのです。
この柔軟性は台湾らしさでもありますが、ブランド店舗やフランチャイズでは問題になりがちです。
つまり、「スピードの裏にある自由さ」と「品質基準の不安定さ」は、表裏一体なのです。
一貫方式を選ぶ前に確認すべき「社内体制」と「実績の深さ」
では、設計施工一貫を選ぶ際に、何を基準に会社を選べばよいのでしょうか。
最も重要なのは、その会社が「本当に設計と施工の両方に専門部署を持っているかどうか」です。
台湾では、“設計もやります”という施工会社が増えていますが、実際にはデザインを外注しているケースもあります。
一見ワンストップでも、実際は複数業者の寄せ集めということも少なくありません。
信頼できる会社の見極め方としては、以下の3点がポイントです。
1つ目は、社内にデザイナーと現場監督が常勤しているか。
2つ目は、同業種(飲食、物販、オフィスなど)での施工実績が豊富か。
3つ目は、設計と施工の担当者が同席する打ち合わせができるか。
これらがクリアされていれば、設計意図の共有がスムーズで、トラブルを防ぎやすくなります。
つまり、「一貫方式だから安心」ではなく、「一貫体制が機能しているか」を見抜くことが、台湾で成功する出店の第一歩なのです。
第2章 設計施工分離の“透明性”と“調整コスト”
― 日本式プロセスは台湾で機能するのか? ―
日本の店舗づくりでは、「設計」と「施工」を分けるのが常識です。
設計者が空間のコンセプトやデザイン意図を描き、施工会社がその図面通りに正確に形にする──
この明確な分業体制が、日本の品質を支えてきました。
一方で、台湾ではこの“日本式の分離方式”がうまく機能しないケースが多々あります。
理由はシンプルで、設計者が「現場監理者」としての責任を持つ文化が薄く、施工側も「図面より現場優先」で動く傾向があるからです。
つまり、設計施工分離は理想的ではありますが、そのまま台湾に持ち込むと、かえって混乱を招くことがあります。
「分離発注」の基本構造と日本企業が安心できる理由
分離方式の最大の魅力は「透明性」です。
設計会社と施工会社が別であることで、見積もりや仕様変更の内容が明確に分けられ、コストや品質のチェックがしやすくなります。
特に日本企業にとっては、「第三者が監理してくれる」ことで安心感が生まれるのです。
設計者はオーナーの立場に立ち、工事の品質・工程・金額を客観的に監理します。
施工側は、図面に基づき正確に作り込むことに集中する。
この“緊張関係”が品質を守る仕組みとなっているのが、日本の建築文化の根幹です。
台湾でもこの方式を採用する企業はありますが、実際には「監理者がいない」「設計と現場が直接つながらない」ケースが多く、形だけの分離になっていることが多いのが現実です。
つまり、「分離=安全」とは限らず、その体制がきちんと運用できているかどうかが成否を分けるポイントなのです。
台湾の現場では“監理者不在”が起こりやすい背景
台湾では「監理(かんり)」という概念が日本ほど明確に定義されていません。
設計事務所が図面を引いたあと、現場に立ち会わずに工事が進むことは珍しくなく、実際には「監理者不在」の状態が頻繁に起きます。
設計者は完成写真を見て「ほぼ図面通りですね」と納得し、オーナーも“まあまあ良ければOK”という感覚で終わることが多いのです。
この背景には、台湾の「責任分散型」文化があります。
日本のように「監理者が最終責任を負う」という意識は弱く、トラブルが起きた場合は「現場判断だった」「材料が入らなかった」といった説明で収束してしまうケースもあります。
つまり、制度的な“監理者”がいないために、分離方式が理想的に機能しないのです。
日本企業がこの構造を理解せずに「日本と同じ感覚」で進めてしまうと、「誰も現場を見ていなかった」「施工側の判断で変更されていた」という結果になりかねません。
ここが、台湾で分離発注を行う最大のリスクといえます。
設計者と施工者の“責任のグレーゾーン”問題
日本では、設計と施工の責任範囲が明確です。
しかし、台湾ではその線引きが非常に曖昧です。
たとえば、照明器具の選定ひとつを取っても、「設計者が選ぶ」と考える会社もあれば、「施工側が在庫状況で決める」とする会社もあります。
このように、どちらがどこまで責任を負うのかが曖昧なまま進行すると、最終的に“誰も責任を取らない現場”になります。
実際、「施工側が変更した」「設計者が細かく指定しなかった」と互いに責任を押しつけ合うことは、現在でも日常的に起こっていることです。
さらに、台湾の多くの現場では、設計図面の詳細が日本ほど厳密ではありません。
仕上げ材や寸法精度の指定が曖昧なまま工事が始まるため、施工側の判断余地が大きくなり、結果的に品質ばらつきが生まれます。
つまり、分離方式は“責任の明確化”を狙うものですが、台湾ではむしろ“責任の曖昧化”を招くことがあるのです。
現場との距離が生む“伝達ロス”と“タイムロス”
分離方式では、設計者が直接現場に常駐することはほとんどありません。
そのため、現場での意思決定スピードが著しく遅くなることがあります。
たとえば、天井高の変更や配線位置の調整が必要になった際、施工側は設計者に確認し、設計者はオーナーに確認を取り、承認が出るまで工事が止まるということが頻発します。
台湾では、こうした“待ち時間”を嫌う傾向が非常に強いです。
現場は「その日のうちに判断してほしい」と求め、オーナーは「任せたはずなのに」と不満を抱く。
この「スピード感のズレ」こそが、台湾で分離発注を採用する際の最大の課題です。
また、設計図面上の指示が中国語で正確に伝わらないケースもあります。
特に日本から設計図を持ち込む場合、「日本語図面+翻訳不足+現場通訳なし」の三重苦で、現場が混乱することも少なくありません。
分離方式を選ぶ場合は、単なる図面翻訳だけでなく、“設計通訳”として機能できる人材を確保することが不可欠です。
分離方式を成功させるための「台湾流ディレクション」術
では、どうすれば分離方式でも台湾でうまくプロジェクトを進められるのでしょうか。
その鍵は、「日本的な管理」を押しつけるのではなく、「台湾的なスピード」と「日本的な品質意識」を融合させることにあります。
具体的には、次の3点が重要です。
- ローカル監督との連携体制を構築すること。
日本からの設計者が定期的に現場確認し、台湾側の監督と共同で品質をチェックする。いわば、“二重監理”の形をとるのが理想です。 - 設計意図を「図面」ではなく「視覚情報」で共有すること。
台湾では、図面よりも完成イメージ(CGパースやサンプルボード)のほうが理解されやすい文化があります。「どんな空気感を作りたいか」を視覚的に共有することで、施工側の判断がぶれにくくなります。 - 決定権を現場に近い位置に置くこと。
全てを日本本社で承認していてはスピードが出ません。台湾現地の担当者に、ある程度の裁量と判断権限を与えることで、分離方式でも機動力が生まれます。
つまり、「分離=監理者が全部見張る」という発想ではなく、「設計者が現場を信頼し、現場が設計意図を理解する」関係を築くこと。
それが、台湾で分離発注を成功させるための唯一の方法です。
第3章 コスト構造から見る両方式のリアル
― 安いと思ったら高くつく?数字に隠れた真実 ―
台湾で内装工事を進める際、日本企業が最も重視するのは「コスト感」です。
見積書を比較すると、設計施工一貫のほうが明らかに安く見える──この印象が、実際に多くの発注判断を左右しています。
しかし、現場を知る立場から言えば、「安く見える」ことと「実際に安い」ことはまったくの別問題です。
台湾の見積書は日本とは書式も思想も異なり、数字の裏には文化的な差や慣習的な省略が隠れています。
「一貫方式は設計費ゼロでお得」「分離方式は設計費が高い」と単純に判断してしまうと、後から“想定外の出費”に直面することも少なくありません。
一貫方式のコストが低く見える理由
台湾の内装市場で設計施工一貫が人気を集める最大の理由のひとつが、「初期見積もりの安さ」です。
多くの一貫会社は「設計費無料」「デザイン込みでこの価格」と提示します。
オーナー側からすれば、設計費を別途支払う必要がない分、心理的なハードルが下がります。
しかし、これは単に「見積もり上で設計費を分離していない」だけの話であり、実際には設計の工数はしっかりとコストに含まれています。
しかも、その設計コストは“他項目に上乗せされている”ケースが多く、詳細内訳が見えづらい構造になっています。
例えば「木工工事」や「電気工事」の単価に設計分が吸収されており、結果的に総額では決して安くないという事例もあります。
また、台湾では「見積もり時点では最低限」「追加で実費」という考え方が一般的です。
つまり、最初の見積金額は“スタートライン”であり、“ゴールの金額”ではありません。
スピード優先の文化が、この“ざっくり見積もり”を常態化させているのです。
設計費ゼロの裏にある「見えない設計コスト」
設計費無料をうたう会社は多いですが、これは必ずしも「設計を丁寧にやってくれる」という意味ではありません。
むしろ、図面の作成にかける時間を極力削減し、最小限の情報で工事を始めるケースが多く見られます。
その結果、現場での変更や調整が頻発し、最終的に「修正費」「手直し費」「追加材料費」としてコストが積み上がるのです。
筆者が見た例では、設計費を削った分、現場での打ち合わせ時間が増え、職人の手待ちや材料再手配が発生し、結果的に10〜15%のコスト増になったケースもあります。
つまり、「設計費を払わない代わりに現場で払う」──これが台湾における“一貫方式の現実的コスト構造”なのです。
また、日本のブランド店舗では細部のデザイン精度が求められます。
照明の角度、什器の高さ、素材の継ぎ目──こうした細部設計を省くと、ブランドクオリティが損なわれます。
「設計費ゼロ」で失うのは、単なる数字ではなく、ブランドの再現性そのものなのです。
分離方式における「監理費」と「調整費」の正体
一方で、分離方式の見積もりを見ると、「監理費」「設計調整費」など、日本ではあまり見慣れない項目が並ぶことがあります。
台湾では、分離方式を選ぶと「現地調整のための人件費」が発生するのが一般的です。
これは、設計者が現場を直接管理できないため、現地スタッフを配置する必要があるからです。
この“監理費”は一見すると無駄に見えるかもしれませんが、実際には工事トラブルの保険のようなものです。
品質不良や施工ミスが起こった場合、監理者が早期に発見・是正できれば、結果的に全体コストを抑えることができます。
また、「設計調整費」は、図面を現地仕様に合わせるための翻訳・再構成の手間を意味します。
日本の施工基準を台湾でそのまま使うことはできないため、配線や寸法、材料調達ルートを調整する必要があります。
つまり、分離方式では“事前の調整”にコストがかかりますが、その分“現場トラブルの後処理コスト”が減るという構造です。
台湾の追加工事リスク──契約前に確認すべき3つの項目
台湾の工事契約で最も多いトラブルが「追加費用」です。
一貫方式の場合、「ここは見積範囲外」「仕様変更扱い」と言われて追加請求されることが珍しくありません。
これは、初期見積の段階で仕様が十分に確定していないことが原因です。
契約前に確認すべきポイントは、次の3つです。
- 見積書の“範囲外工事”を必ず明記すること。
たとえば、電気配線や給排水工事、家具据付などが別扱いになっていないかを確認します。 - 仕上げ材の指定とグレードを細かく明文化すること。
台湾では「木工板」と一言でまとめられることが多く、実際には品質差が大きい。同じ言葉でもグレードが違えば価格も倍近く変わります。 - 変更時の単価基準を契約書に明記すること。
後から「その都度見積もり」ではなく、「単価表」に基づいて追加計算する仕組みをつくると安心です。
こうした契約管理を怠ると、完成後に“見積より20%高くなった”という事態も珍しくありません。
台湾でコストを制御するためには、見積より契約を重視する姿勢が不可欠です。
“安さ”ではなく“再現性”で判断する出店コストの見方
結局のところ、台湾での店舗出店における“良いコスト”とは何でしょうか。
筆者の経験上、それは「次の店舗でも同じ品質を再現できるコスト」です。
初回は安くても、二店舗目以降で同じ仕上がりが出せない場合、それは“偶然の安さ”にすぎません。
設計施工一貫の強みは、担当者の裁量で素早く対応できる点にありますが、その属人的な対応は「再現性の欠如」と表裏一体です。
一方で分離方式は、ルールや図面をしっかり整備するため、次の出店時にも同じ品質を再現しやすい。
初期コストは高くても、長期的に見れば“安定したブランド再現”という形で回収できます。
台湾で成功している日系チェーンは、この「再現性コスト」に投資しています。
つまり、安さではなく、同品質を維持できる体制にいくら払えるか──
ここが、台湾進出の成否を分ける判断軸なのです。
第4章 信頼関係で決まる「成功する発注形態」
― パートナー選びが8割を決める ―
台湾で店舗の内装設計や工事を進めていると、同じ会社、同じ金額でも「結果がまったく違う」という現象が起こります。
図面通りに仕上がる現場もあれば、細部が雑で仕上がりが安っぽくなる現場もある。
この差を生む最大の要因は、発注形態ではなく「人間関係の質」にあります。
日本では「契約」と「図面」で信頼を築きますが、台湾ではそれよりも「人」と「関係性」が優先されます。
どんなに条件を整えても、担当者との信頼がなければスムーズに進みません。
逆に、信頼があれば、設計施工一貫でも分離方式でも驚くほど柔軟で高品質な仕事が実現します。
日本的な“契約信頼”と台湾的な“人間信頼”の違い
日本の設計・施工業界では、「契約書に書かれたこと」がすべてです。
図面に記載されていれば、施工者はその通りに造り、記載がなければ追加扱いになる──
こうした明確なルールの中で信頼が形成されます。
一方、台湾では「人間関係がすべての基本」です。
契約書よりも「相手が信頼できる人か」「誠実に対応してくれるか」が重視されます。
たとえば、契約書に細かく書かれていても、担当者が不誠実だと現場はうまく回りません。
逆に、契約書が曖昧でも、担当者がオーナーの意図をくみ取り、現場に反映してくれるケースも多々あります。
つまり、台湾では「契約で縛る」より「信頼で動かす」文化が根づいています。
この違いを理解せずに「日本的な管理」を押し通そうとすると、相手は“信用されていない”と感じ、関係が硬直化してしまいます。
台湾では、まず“人としての関係”を築き、その上に契約と工程を重ねていく──
この順序が極めて重要なのです。
担当者の「レスポンス力」が現場品質を左右する
台湾で内装プロジェクトを進める際、成功の鍵を握るのは「誰が担当するか」です。
同じ会社でも、担当者によって仕上がりが大きく変わります。
筆者が経験した中でも、レスポンスが早く、判断が的確な担当者に当たった現場は、トラブルが少なく納期も正確でした。
台湾では、現場での意思決定が非常に早いため、担当者がオーナーとの連絡を怠ると、気づいた時には仕様が変わっていたということが起こります。
この“情報の即時共有”こそ、台湾での品質を守る最重要ポイントです。
また、メールよりもLINEなどのメッセンジャーアプリでのやり取りが主流である点にも注意が必要です。
設計変更や納品確認なども、チャットで進められることが多いため、レスポンス力=現場コントロール力と言っても過言ではありません。
つまり、発注先の会社を選ぶ際には、ブランド名よりも“担当者の動き方”を見ること。
その担当者が「即時対応できるタイプか」「誠実に報告してくれるか」が、結果を左右します。
設計者と施工者の“チーム力”をどう見抜くか
台湾では、一見「設計施工一貫」と書かれていても、実際には設計と施工が別チームというケースもあります。
この場合、社内で情報共有が不十分だと、設計意図が現場に正確に伝わらず、仕上がりに差が出ます。
したがって、発注前の段階で「設計と施工がどのように連携しているか」を見抜くことが非常に大切です。
見極めのポイントは、“打ち合わせに誰が参加しているか”です。
信頼できる会社ほど、最初の打ち合わせから設計者・現場監督・営業担当が全員そろって出席します。
一方、営業だけが出てきて「工事の詳細はあとで技術部が確認します」といった場合は注意が必要です。
また、施工チームが固定メンバーかどうかもチェックポイントです。
台湾では職人が外注制の場合も多く、現場ごとに職人が変わると品質のバラつきが大きくなります。
安定したチームを抱えている会社ほど、仕上がりの再現性が高いのです。
つまり、「どんな会社か」よりも「どんなチームで動くか」。
そのチームの内部連携こそが、台湾での設計施工一貫・分離を問わず、成功を左右する要素です。
日本企業が信頼を得るために意識すべき3つの姿勢
台湾でプロジェクトを進めると、しばしば「日本企業は細かすぎる」「変更が多い」と言われます。
これは、品質を守るために当然の要求なのですが、台湾側には“管理されている”と映ることがあります。
良好な関係を築くためには、日本側も姿勢を少し変える必要があります。
ポイントは、次の3つです。
- 「指示」ではなく「共有」の姿勢をとること。
たとえば、「こうしてください」ではなく「こうしたい理由を説明する」だけで、相手の受け止め方が変わります。 - 完璧を求めすぎず、現地の事情を尊重すること。
材料の入手難や湿度条件など、日本では当たり前でも台湾では困難なことがあります。その現実を理解した上で、最善を共に考える姿勢が信頼を深めます。 - 感謝と称賛を言葉にすること。
台湾では「ありがとう」「さすがですね」といった言葉を大切にします。現場スタッフをねぎらうことで、チーム全体の士気が上がり、品質も自然と向上します。
信頼は一方通行ではなく、双方向の努力で育ちます。
日本的な管理力に、台湾的な“関係づくり”を掛け合わせることが、真の成功の鍵です。
成功事例に共通する「日台混成チーム」の力
近年、台湾で成功している日系店舗の多くは、「日台混成チーム」を採用しています。
設計段階から日本人デザイナーと台湾人設計者が協働し、現場監督も日台両方の担当者が立ち会う。
この形は、一見コストがかかるように見えますが、実際にはトラブルが減り、工期短縮にもつながります。
特に有効なのが、「設計は日本、施工は台湾」「監理は日台共同」というハイブリッド体制です。
台湾側は現場の事情に精通しており、日本側はブランド基準を把握している。
両者が協働することで、品質・コスト・スピードのバランスが取れるのです。
成功している現場では、週次でオンラインミーティングを行い、写真や動画で進捗を共有しています。
図面上のやり取りではなく、現場の“空気”を共有することで、言語や文化の壁を超えた連携が実現します。
日台の価値観が違うからこそ、双方の強みを生かすチーム設計が不可欠です。
「発注形態」よりも「チーム形態」を整える──これこそが、台湾店舗出店を成功させる最も確実な方法なのです。
第5章 結論:台湾で勝つための最適解は“ハイブリッド型”
― 一貫でも分離でもない、第3の選択肢 ―
ここまで見てきたように、台湾の店舗づくりでは「設計施工一貫」と「設計施工分離」のどちらにも一長一短があります。
一貫方式はスピードと柔軟性に優れますが、品質基準が曖昧になりやすい。
分離方式は透明性と管理性に優れますが、台湾の商習慣とスピード感にはなじみにくい。
では、両方のメリットを活かす方法はないのでしょうか。
実は近年、台湾で日系企業が増やしているのが、「ハイブリッド型」と呼ばれる方式です。
これは、設計施工一貫を基本にしながらも、日本側が監理・品質基準の部分を主導するモデル。
つまり、「日本式の監理」と「台湾式のスピード」を両立させるやり方です。
一貫+監理=品質とスピードを両立する新方式
ハイブリッド型の基本構造は、「設計施工一貫+第三者監理」です。
つまり、台湾の設計施工会社にワンストップで発注しつつ、日本側の設計者または監理者が品質と進捗を定期的にチェックします。
この方式の最大の特徴は、現場の判断スピードを落とさずに、日本品質の管理を維持できる点にあります。
たとえば、台湾の現場は即断即決を求めますが、監理者が週1回リモートで確認を行う体制を整えれば、設計意図を逸脱するリスクを防げます。
一貫方式にありがちな「現場まかせ」「変更の連鎖」を、監理というフィルターで制御するのです。
この仕組みを導入した日系カフェブランドでは、初期工期を1週間短縮しつつ、日本本社のデザイン基準を維持することに成功しました。
つまり、“スピード”と“精度”を両立できる唯一の方式が、このハイブリッド型なのです。
設計は日本、施工は台湾──リモート時代の新スタイル
コロナ禍以降、オンライン会議やクラウド図面管理が当たり前となり、設計と施工の地理的な壁が大幅に低くなりました。
これにより、「設計は日本チーム」「施工は台湾チーム」という国境を越えた協業モデルが急速に広がっています。
日本側はコンセプトデザインと基本設計を担い、台湾側が現地の施工図面を起こし、現場調整を担当する。
両者はクラウド上で図面や3Dモデルを共有し、リアルタイムに修正を加えていきます。
この“分業の共創化”によって、台湾特有のスピード文化を損なわずに、日本的な精密設計を反映できるのです。
実際、筆者が関わったプロジェクトでも、台湾側が現場監督と職人を指揮し、日本側がCGパースとマテリアルサンプルで最終判断を行うスタイルを採用しました。
結果、施工精度が向上し、材料ロスも削減。コスト・納期・品質の三拍子がそろいました。
リモート環境を活用すれば、国境を越えたハイブリッド体制は決して難しくありません。
“日本基準”を現場に落とし込むコミュニケーション設計
ハイブリッド型を成功させるうえで欠かせないのが、「コミュニケーション設計」です。
日本側の基準や意図を台湾の職人に理解してもらうには、単に図面や仕様書を翻訳するだけでは不十分です。
必要なのは、“伝え方”の設計です。
台湾の現場では、「なぜその仕様にするのか」を説明すると、理解と納得が深まります。
たとえば「巾木を細くしたい」ではなく、「空間を広く見せたいから巾木を細くしたい」と理由を伝える。
この一言があるだけで、現場は創意工夫で対応してくれます。
また、図面のほかに「施工サンプル」や「写真集」を共有するのも効果的です。
日本では常識でも台湾では見慣れない納まりや仕上げが多いため、視覚的に伝えることが最も確実です。
つまり、ハイブリッド型の本質は、“文化翻訳”としてのコミュニケーション力にあるのです。
台湾現場で成果を出すための「信頼循環モデル」とは
ハイブリッド型の成功事例には、ある共通点があります。
それは、「信頼が循環している」ということです。
日本側が台湾側を監視するのではなく、信頼して任せ、台湾側がその信頼に応える──
この相互循環が、現場のモチベーションを高めます。
信頼循環モデルとは、次のような構造を指します。
- 日本側が明確な設計意図を示す
- 台湾側がそれを現場レベルで最適化する
- 施工後、日本側が成果を称賛・共有する
このサイクルを繰り返すことで、台湾側のチームは「日本品質」を自ら学び、次のプロジェクトでより高い精度を発揮します。
つまり、一度の成功体験が“学習資産”となり、双方の関係が成熟していくのです。
これは単なる発注モデルではなく、“共に育つ関係性”をデザインする仕組みです。
ハイブリッド型の真価は、この「信頼の循環」によって、プロジェクトごとに成長が積み重なる点にあります。
日台協業の未来──「共創」こそが真の最適解
最終的に、台湾での店舗づくりを成功させる鍵は、“どちらの方式を選ぶか”ではありません。
重要なのは、日台それぞれの強みを組み合わせ、共創(Co-Creation) の関係を築けるかどうかです。
日本は、精密な設計・緻密な管理・ブランド再現性に優れています。
台湾は、スピード・柔軟性・現場判断の的確さで勝っています。
どちらが上ではなく、どちらも欠かせない。
この二つの文化が融合したとき、初めて「台湾における日本品質」が実現します。
たとえば、日本側が「細部へのこだわり」を教え、台湾側が「即断即決の現場力」で補う。
この相互補完ができれば、もはや国境や文化の違いは障害ではなく、価値創造の源になります。
これからの台湾出店戦略に求められるのは、“どちらの方式を選ぶか”ではなく、“どのように協働して理想の空間を生み出すか”。
その答えこそが、ハイブリッド型、すなわち日台共創の未来型発注モデルなのです。
まとめ:「スピード」か、それとも「品質」か。その答えは“信頼設計”
台湾で店舗をつくるとき、最初に直面するのが「設計施工を一貫で頼むか、それとも分離するか」という選択です。
多くの日本企業が、効率とリスク回避の間で迷います。
しかし実際の現場を見続けてきた立場から断言できるのは──
この問いの答えは、発注形態そのものにはないということです。
真の成否を分けるのは、「どの方式を選ぶか」ではなく、「誰とどう進めるか」、そして「どんな信頼関係を築けるか」にあります。
設計施工一貫には、台湾らしいスピードと柔軟性があります。
オーナーがその場で決め、職人が即座に形にする。
この現場感覚は、変化の激しい台湾市場では大きな強みです。
しかしその一方で、品質基準の曖昧さや責任範囲の不明確さが、後々トラブルを生むこともあります。
一方の設計施工分離は、透明性と品質管理に優れます。
日本企業にとっては馴染みがあり、安心できる発注方法です。
しかし台湾では、監理文化がまだ十分に浸透しておらず、スピード感が合わないことも多い。
理想を追いすぎると、現場とのズレが拡大し、かえって非効率になることもあります。
だからこそ、今注目されているのが“ハイブリッド型”です。
設計施工一貫のスピードを生かしながら、日本側が監理・品質基準をサポートする。
いわば「一貫+監理」の形で、両者の強みを融合させる方法です。
これは単なる折衷案ではなく、新しい「協働型モデル」です。
日本の設計思想を軸に、台湾の現場力で実現する。
日本側は指示ではなく“意図”を伝え、台湾側は創意工夫でそれを形にする。
その過程で生まれる“相互理解”が、最も強固な信頼関係を築いていきます。
台湾で成功している日系ブランドの多くは、この「信頼設計」を実践しています。
契約書よりもコミュニケーション、指示よりも共有、管理よりも協働。
その一歩を踏み出すことで、台湾のパートナーは「監視される相手」から「共に創る仲間」へと変わります。
そして、この信頼関係こそが、台湾で日本品質を再現する唯一の方法です。
スピードでもなく、コストでもなく、“信頼”こそが最大の投資効果を生む資源なのです。
いま、台湾のインテリア市場は、確実に進化しています。
設計者も施工者も、日本的な品質基準を理解し、学び、吸収しようとしています。
そんな時代に求められているのは、「指導」ではなく「共創」。
“日本式”を押しつけるのではなく、“台湾式”と融合させる柔軟な発想です。
あなたが次に台湾で店舗をつくるとき──
「一貫か分離か」ではなく、
「どうすれば信頼と品質を両立できるか」という視点で考えてください。
そして、信頼できる現地パートナーと共に、日本と台湾の“いいとこ取り”の店舗づくりを実現してください。
その挑戦こそが、日台のデザイン文化をつなぎ、アジア全体に新しい店舗づくりのスタンダードを生み出す一歩となるはずです。