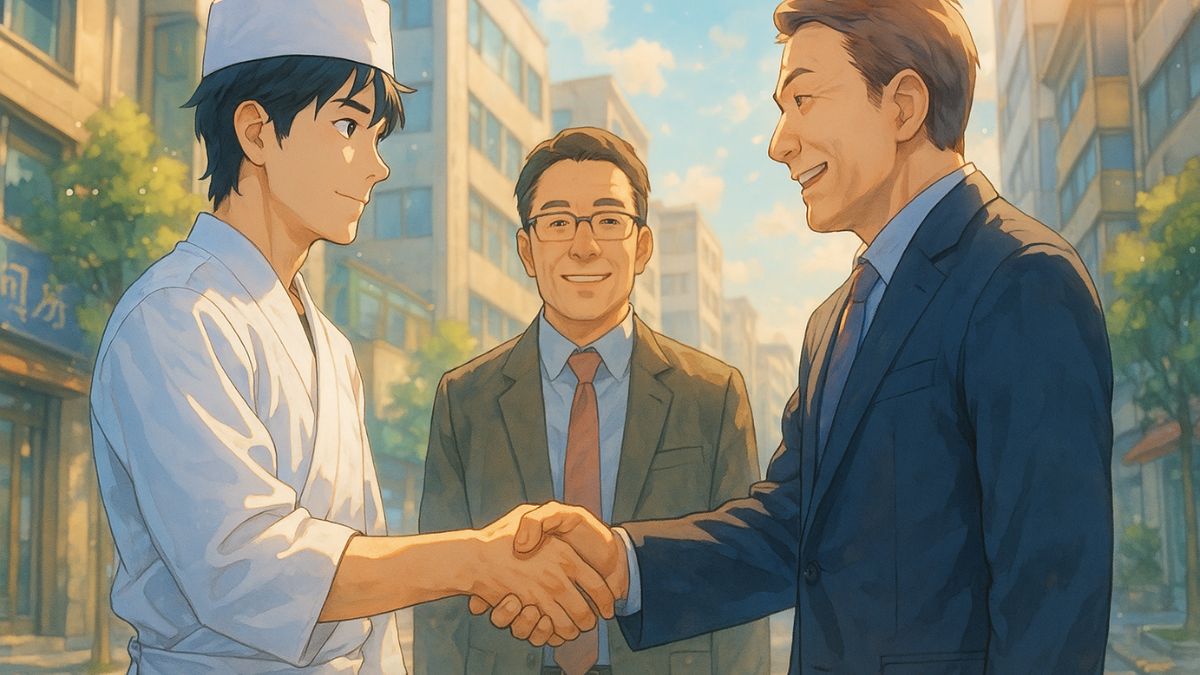台湾での店舗出店や内装設計を成功に導く最大の鍵は「誰と、どうつながるか」です。
日本のように契約や仕様書で全てが動く世界ではなく、台湾では“人と人の信頼関係”こそが工事の進行・コスト・品質を左右します。
単なる「コネ」ではなく、信頼をベースにした長期的な関係づくりが、あなたのビジネスをどのように変えるのか──
その具体的な方法について考えてみます。
第1章 台湾ビジネスの要は「人脈」にあり
台湾での店舗出店や内装工事を成功させるには、図面の美しさや設計精度だけでは足りません。
実際の現場を動かし、スケジュールを前に進めるのは、人と人との信頼関係=ネットワークです。
日本では契約書や仕様書があれば物事が進むケースが多いですが、台湾では“誰とつながっているか”が大きな影響を持ちます。
なぜ台湾では「コネ」ではなく「信頼関係」が重要なのか
日本人の感覚で「コネ」というと、少し後ろめたい響きがありますが、台湾ではそれが“信頼の証”として機能しています。
重要なのは、単なる紹介ではなく「互いに面倒を見合う」関係性を築けるかどうか。
たとえば、ある店舗オーナーが「内装工事会社を紹介してほしい」と知人に頼むとき、紹介する側はその会社の仕事ぶりだけでなく「この人と組んでトラブルにならないか」まで考えます。
もしトラブルが起きれば、紹介者の信用まで失われるからです。
つまり、台湾では“紹介する=自分の信用を差し出す行為”。
そのため、最初の信頼を得るには、約束を守り、誠実な対応を積み重ねることが何よりも大切なのです。
日本企業が誤解しやすい「台湾の人付き合い」3つの特徴
日本企業が台湾で苦労する理由のひとつが、人間関係の“距離感の違い”です。
台湾では初対面でもフレンドリーに話しかけてくれる一方で、その裏に深い信頼があるとは限りません。
第一に、台湾では「早い段階で関係を作るが、信頼の定着は遅い」という特徴があります。
笑顔で握手を交わしても、相手はあなたを“観察中”です。
第二に、「友人を介した関係」が重視される点です。
直接的な営業よりも、誰かの紹介を経て出会った方が圧倒的に信頼を得やすい。
第三に、「食事や会話の時間」が関係構築に欠かせません。
打ち合わせが終わっても、軽いお茶や夕食を共にすることが、ビジネスを円滑にする大切な時間なのです。
この“距離の取り方”を誤ると、「ビジネスライクで冷たい」と思われてしまうこともあるので注意が必要です。
現地ネットワークが強い設計会社を見分けるコツ
台湾で設計会社を選ぶ際、図面のクオリティやデザインセンスだけで判断するのは危険です。
現地で成功している設計会社の共通点は、「人脈が広く、信頼されている」こと。
たとえば、工務店、行政、材料業者、消防署とのつながりがある会社ほど、工期を短縮し、問題を早期に解決できます。
台湾では申請や検査が現場ごとに異なるため、行政窓口に詳しい担当者がいることも大きな強みになります。
また、地場の施工会社やメーカーから「○○設計は仕事が丁寧」と評判が立っているかも重要な指標です。
口コミや同業者間の評価は、台湾ではとても正直です。
つまり、良い設計会社とは“設計力”と“人間関係力”を兼ね備えた会社。
店舗設計や内装工事の現場では、このネットワーク力がプロジェクトの安定性を決定づけます。
信頼を得る第一歩は「紹介者」をどう作るかにある
日本企業が台湾で最初に直面する課題は、「誰を通して人とつながるか」です。
いきなり飛び込みで問い合わせをしても、対応は表面的になりがちです。
台湾では、共通の知人を介して紹介を受けることが、最初の信頼構築につながります。
具体的には、
- 台湾で既に取引経験のある日本企業
- 台湾在住の日本人デザイナーやコンサルタント
- 商工会やJETRO、現地ビジネス協会
などを通じて紹介をもらうのが効果的です。
紹介者が信頼されていればいるほど、その信用はあなたにも引き継がれます。
ここでのポイントは、「紹介を受けた後の礼儀」です。
感謝のメッセージや小さな報告を忘れずに行うことで、関係が次の紹介へと発展していくのです。
縁をつなぐ台湾式のビジネスコミュニケーション術
台湾のビジネス現場では、形式的なプレゼンよりも「雑談」「気遣い」「ユーモア」が重視されます。
日本企業が硬い雰囲気のままで臨むと、相手との間に距離が生まれてしまいます。
たとえば、打ち合わせの冒頭で「この近くでおすすめのランチありますか?」と聞くだけでも場が和みます。
台湾人は話題の中に“共感”を見つけるのが得意で、そこで笑顔が生まれれば一気に信頼が深まります。
また、メールよりLINEやWhatsAppでやり取りをするケースも多く、即時性と親しみが重視されます。
日本的な「かしこまった文体」よりも、「気軽に、でも丁寧に」が台湾流。
そして、もうひとつのコツは「顔を合わせる回数を増やすこと」。
台湾では“face to face”の信頼が最も価値を持ちます。
デジタルだけで完結せず、可能な限り現地に足を運ぶ姿勢こそ、あなたの誠意を伝える最大の手段なのです。
第2章 設計・施工の現場で生きるネットワーク
台湾で店舗を出店する際、図面が完成したあとが本当のスタートです。
設計図はあくまで理想であり、現場は生き物のように日々変化します。
日本のように「仕様書通りに進めれば予定通り完成する」という世界ではなく、台湾では「誰と一緒に現場を進めるか」がすべてを左右します。
現場監督、職人、資材業者、オーナー、設計士——
それぞれが密に連携しなければ、図面通りの空間は実現しません。
台湾現場の“人間関係型マネジメント”を理解する
日本では工程表と進捗会議によって現場が進みますが、台湾ではそれだけでは不十分です。
ここでは、“人間関係の温度”が進捗を左右するといっても過言ではありません。
たとえば、電気工事が少し遅れているとき、書面で催促しても動かない場合があります。
しかし、監督や設計者が直接電話をして「明日の午前までにここを終わらせたいんだけど、手伝える?」と柔らかく伝えると、意外にもすぐ動いてくれることがあります。
台湾では、関係が良好であれば“頼みごと”が通じやすく、逆に距離があると「次の案件まで対応を後回しにされる」こともあります。
つまり台湾現場は、「管理する現場」ではなく「関係で動く現場」。
工程管理表以上に、日々の対話と関係維持が最強のマネジメント手法なのです。
設計者・職人・オーナーの三角関係を円滑に保つ術
台湾の現場では、設計者、職人、オーナーの三者がそれぞれ強い意見を持ちます。
オーナーが現場に頻繁に来て急な変更を指示するのは、台湾ではごく普通の光景です。
このとき設計者が図面を守りすぎると、職人が困惑し、作業が止まる。
一方でオーナーの要望をすぐに受け入れると、全体の整合性が崩れます。
この微妙なバランスを取るには、信頼関係でつながった現場ネットワークが不可欠です。
たとえば、職人に「設計側の意図」を丁寧に伝え、同時にオーナーには「現場の事情」を説明できるような通訳的立場の人間が重要です。
日本式の「立場を明確にする」管理よりも、台湾では「相互理解を橋渡しする」姿勢が求められます。
これがうまく機能すると、現場全体に一体感が生まれ、スピードも品質も格段に上がるのです。
「困ったときに誰に電話できるか」が成功を決める
台湾の内装現場では、予期せぬトラブルが頻発します。
資材の納期遅れ、天候による作業中断、突然の設計変更、行政検査の追加対応…
こうしたときに、「すぐに動ける関係者がいるか」で結果がまったく違います。
たとえば、ある内装現場で壁紙の在庫が急に切れた際、担当者がすぐに壁紙屋に電話し、「明日朝に倉庫から運べないか」と交渉。
その壁紙屋が以前からの知り合いで、「あなたの現場なら優先して出すよ」と即答してくれたことで、工程が1日も遅れずに済んだ例があります。
台湾では、こうした“臨機応変な助け合い”が日常です。
書類や契約では解決できない小さな問題ほど、「関係の深さ」が効いてくるのです。
現場を動かすのはスケジュール表ではなく、人の心と信頼のライン。
電話一本で助けてもらえる関係をどれだけ築けるかが、現場の強さを決めます。
台湾の施工現場で頼りになる“キーパーソン”とは
台湾の施工現場では、表に出てこない“影のキーパーソン”が存在します。
それは、現場を取り仕切る熟練の職人リーダーや、資材業者の営業担当、あるいは行政検査担当とつながりの深い監督などです。
こうした人物は、現場全体の空気を読みながら調整を行う“潤滑油”のような存在です。
たとえば、「消防検査の担当官が急に日程を変更した」とき、そのキーパーソンが別ルートで情報を得て、前日に調整を済ませておくこともあります。
彼らは名刺には書かれない力を持っています。
したがって、日本企業が台湾で現場を進めるときは、「誰が現場の信頼を集めているか」を早めに見極め、その人物をリスペクトし、関係を深めることが非常に重要です。
台湾では「公式な立場」よりも「人としての信頼」が現場を動かします。
ネットワークが「トラブルを防ぐ最強の保険」になる
日本企業が台湾で内装プロジェクトを行う際、もっとも多い悩みのひとつが“予期せぬトラブル”です。
配線の取り回し、天井高の誤差、素材の色違い、行政の追加指摘…
これらは決して避けられません。
しかし、トラブルが起きたとき、ネットワークがあるかないかで結果は180度違います。
信頼関係があれば、職人も「今回は助けるよ」と残業をしてくれたり、業者が「他の現場の分を融通する」と対応してくれることもあります。
逆に、関係が希薄だと「契約外だからできません」と突き放されてしまうのが現実です。
つまり、台湾現場におけるネットワークは、金銭的コストを超えた“信頼の保険”。
日本企業が台湾で複数店舗を展開するなら、この“信頼資産”をどう積み上げるかが、次の店舗のスピードと成功率を大きく左右するのです。
第3章 サプライヤーと行政ネットワークの構築術
台湾で店舗を出店する際、設計や施工の質を左右するのは、現場だけではありません。
内装資材の供給スピード、行政手続きのスムーズさ、申請書類の通りやすさ──
これらを支えているのは、現地サプライヤーや行政担当者とのネットワークです。
内装工事を成功に導くためには、図面を描く力よりも、人と人をつなぐ力がものを言う場面が少なくありません。
台湾の内装資材市場の“顔の見える取引”を知る
台湾の内装資材の流通構造は、日本のように大手商社が一括で扱う形ではなく、中小の材料商や製作所が地域ごとに密集しているのが特徴です。
台北、台中、高雄といった都市には、木工・金物・照明・タイル・ガラスなどの専門市場があり、そこでは価格交渉も柔軟に行われます。
しかし、単に安さを追求すると痛い目を見ることもあります。
なぜなら台湾では、「誰から買うか」で品質や納期の信頼度が変わるからです。
信頼のある材料商とは、急な追加発注にも柔軟に対応してくれたり、欠品時に代替品をすぐ提案してくれたりします。
その背景には、「顔を知っている取引」の文化があります。
初めて会うよりも何度も現場で顔を合わせてきた相手の方が、圧倒的に優先されるのです。
つまり、台湾で成功する資材調達とは、“価格交渉”よりも“関係交渉”。
人と人の信頼が最も安定した供給ラインを生み出します。
サプライヤー選びは「価格」より「人柄」で決まる
台湾の材料業者を見ていると、価格表だけでは測れない「人の温度」があります。
たとえば、金物を扱う業者でも、「この担当者は現場の苦労を理解している」「この人は利益優先で柔軟性がない」といった差がはっきり出ます。
日本企業の感覚では「契約条件がすべて」となりがちですが、台湾では**「人柄が契約を支える」と言っても過言ではありません。
店舗出店スケジュールがタイトな場合、資材調達でトラブルが起こると全体工程に大きな影響を及ぼします。
そんな時、「あの担当ならなんとかしてくれる」という関係があるかどうかで結果はまったく違います。
筆者自身も、台北の内装現場で塗装材が急に不足した際、以前から付き合いのある塗料商が「夜でも倉庫を開けるから取りに来て」と対応してくれたことがあります。
この柔軟さは、“信頼関係の貯金”があって初めて得られるものです。
台湾でパートナーを選ぶときは、価格よりも“人間として信頼できるか”を重視すべきなのです。
行政手続きは「誰に頼むか」でスピードが変わる
台湾での「店舗出店」「店舗改装」では、各市の建築管理課や消防局、商業登記など、さまざまな行政手続きが関係します。
ここでよくある誤解が、「書類を揃えれば自動的に通るだろう」という日本的発想です。
台湾では、“担当官によって判断が異なる”という現実があります。
同じ内容の図面でも、担当者によって指摘の細かさが違う。
追加資料を求められることもあれば、すんなり通ることもある。
その違いを決めるのが、“行政ネットワーク”です。
経験豊富な設計会社や監理者は、行政側とのコミュニケーションを積み重ね、「どうすればスムーズに通るか」を肌で知っています。
また、行政職員の信頼を得るには、誠実で丁寧な対応が欠かせません。
書類を後回しにしたり、説明を怠ったりすると、次回から“要注意案件”として扱われてしまいます。
台湾での行政対応は、「書類勝負」ではなく「人間関係勝負」。
信頼できる設計会社や代理申請者を通すことが、最短ルートでの承認につながるのです。
現地の材料屋・製作所との関係を築く実践方法
台湾の内装現場で安定的に成果を上げている日本企業は、共通して“現地職人・製作所と直接会う”努力をしています。
工場を訪問し、製品を見せてもらい、職人の手仕事を理解する──
その積み重ねが信頼の礎になります。
また、台湾では「紹介の連鎖」が強力に働くため、ひとつの工場と良好な関係を築くと、そこから別の協力工場を紹介してもらえることも少なくありません。
この紹介ルートは、ネットワークの輪を広げる最良の手段です。
さらに、台湾の材料屋や職人は「自分の仕事を評価してくれる相手」に心を開きます。
「この仕上げ、とても綺麗ですね」「日本でも通用するレベルです」といった一言が、関係を一気に深めることがあります。
言葉の壁があっても、誠意と敬意を伝える姿勢さえあれば、国籍を越えて強い絆が生まれるのです。
ネットワークを持つ会社がコスト競争で勝つ理由
台湾では、内装工事費を「坪単価」で判断できないケースが多く、同じ規模の案件でも業者によって大きく見積が異なります。
なぜなら、“どのルートで資材を調達するか”によってコスト構造が変わるからです。
長年の付き合いがあるサプライヤーを持つ会社は、仕入れ価格が安定しており、納期トラブルも少ない。
その結果、全体の工程を短縮でき、コストを圧縮できます。
さらに、こうした会社は工期の読みが正確で、追加費用の発生も抑えられるため、結果的に「高品質・低コスト」を実現します。
一方、ネットワークの弱い会社は、資材調達で毎回新しい業者を探すことになり、値段交渉からやり直し。結果として時間もコストもかかります。
つまり、台湾の内装業界では、ネットワークの強さが利益率そのものを左右するのです。
信頼関係の厚みこそが、見積書には現れない“競争優位”を生み出します。
第4章 日本企業が台湾ネットワークを育てる方法
日本企業が台湾で新規出店や内装工事を進める際、最初のハードルは「信頼できる人脈がない」という現実です。
台湾はオープンで親しみやすい国ですが、“すぐ仲良くなれる”ことと“信頼される”ことは別です。
本当の意味で現地から信頼されるには、時間と誠実さ、そして文化的理解が必要になります。
目指すのは「取引先」ではなく「信頼で結ばれた仲間」になることです。
台湾進出初期に“信頼の芽”を育てるステップ
台湾で最初にやるべきことは、「自分を知ってもらうこと」です。
初対面の段階では、肩書きよりも人柄を重視されます。
名刺交換よりも、会話の中でどんな姿勢を持っているかが見られています。
たとえば、商談の前に「台湾で仕事をするのは初めてです」「学ばせてください」という謙虚な一言を添えると、相手は安心感を持ちます。
また、台湾では「紹介文化」が強く、誰を通じて知り合ったかが信頼の入口になります。
最初は、既に台湾に進出している日系企業や、商工会、JETRO、現地コンサルタントなどのネットワークを活用して紹介を受けるのが効果的です。
この段階でのキーワードは「スピードより関係」。
短期的な取引よりも、長期的に一緒に歩めるパートナーを見つける意識が大切です。
信頼の芽は、焦らずゆっくりと時間をかけて育てましょう。
日台合同プロジェクトで信頼を深めるコツ
信頼関係を一気に深める最も効果的な方法が、「共に現場を経験する」ことです。
図面打ち合わせや商談だけでは見えない、人柄や責任感、対応力が、プロジェクトを通じて浮き彫りになります。
台湾の設計会社や施工業者と合同で進めるプロジェクトでは、困難な場面ほど信頼が生まれます。
たとえば、想定外の施工ミスが発生した際に、責任を押し付けず「どうやって解決しようか」と一緒に考える姿勢を見せる。
この“同じ方向を見る関係”が生まれると、相手は次の案件でも「また一緒にやりたい」と感じてくれます。
日本では当たり前の誠実さや丁寧さも、台湾では強い印象を与えます。
合同プロジェクトの目的は“成果物”ではなく、“信頼の蓄積”であると捉えると、日台の関係は長く続くのです。
台湾で信頼される「日本企業のふるまい方」
台湾では、仕事のやり方以上に「人としてどう接するか」が評価されます。
たとえば、メールを返すスピード、打ち合わせ後のフォロー、相手を立てる態度などが信頼を左右します。
また、台湾人は観察力が鋭く、「言葉ではなく態度で誠意を測る」傾向があります。
- 約束した時間を守る
- 現場に足を運び、状況を自分の目で確認する
- 他人の功績を認め、感謝を伝える
これらの当たり前の行動が、実は最も効果的な信頼構築の手段です。
一方で、「日本ではこうなのに」と言ってしまうのは禁句。
台湾には台湾のルールがあり、それを尊重する姿勢が求められます。
相手の文化を理解しようとする努力そのものが、最大の敬意の表れです。
台湾で信頼される日本企業は、常に“柔らかく、芯のある対応”を心がけています。
イベント・展示会・SNSを通じたネットワーク活用
台湾では、ビジネスの出会いは会議室の外にも転がっています。
特にデザイン・建築関連の展示会や業界イベントは、優良な設計会社・施工会社・資材業者と出会う絶好の場です。
イベントで名刺交換した後は、LINEやFacebookなどを使って気軽にメッセージを送ることも一般的。
「先日はありがとうございました。ぜひ次の案件で相談したいです」といったカジュアルなフォローが、関係を自然に深めます。
また、SNSは単なる情報発信だけでなく、「信頼の可視化ツール」として機能します。
現場写真や施工風景を投稿すれば、「この会社はきちんと仕事をしている」と認識され、紹介の機会が増えます。
台湾ではSNSが人脈形成の中心にあり、オフラインとオンラインの両輪で信頼を築くことが今や必須なのです。
紹介される企業になるための“日台信用力”の磨き方
台湾のビジネス社会では、「誰を紹介できるか」がその人の信用を示します。
つまり、紹介される企業になることこそ、最大の評価です。
そのためには、まず「一緒に仕事をして気持ちが良い」と感じてもらうことが前提。
支払いを守る、連絡を早く返す、トラブルがあったら隠さず報告する──
この3つを徹底するだけでも、信用度は格段に上がります。
さらに、現場が終わった後に「今回の工事では助けていただきありがとうございました」と感謝を伝えることも大切です。
台湾では、“終わった後の関係の扱い方”が次につながるかどうかを決めます。
感謝を言葉にし、相手をリスペクトする姿勢を続けると、やがて相手の口から「信頼できる日本企業がある」と次の紹介が生まれる。
こうして広がる紹介の連鎖こそが、台湾市場での最大の資産なのです。
第5章 ネットワークをビジネスの力に変える
ここまでで、日本企業が台湾でネットワークを築くための基礎や方法を見てきました。
しかし、信頼関係を築くだけでは十分ではありません。
次の段階では、それを「ビジネスの成果に結びつける力」が必要です。
台湾のビジネス環境では、人脈は“飾り”ではなく“資産”。
上手に育てれば、案件を生み、問題を解決し、新しい機会をもたらします。
ネットワークを「売上につなげる」考え方
台湾でのビジネスネットワークは、単なる付き合いではなく「案件創出の仕組み」に転化できます。
多くの日本企業が陥りがちな誤りは、「関係を持っていても、仕事に発展しない」という状態です。
これは、信頼関係を“維持”しているだけで、“活用”できていないことが原因です。
まず重要なのは、「この関係が誰のどんな課題を解決できるか」という視点を持つこと。
たとえば、設計会社のネットワークを使って、店舗改装を検討しているオーナーを紹介してもらう。
あるいは、工事会社のパートナーから資材商を紹介してもらい、仕入れコストを下げる。
信頼関係は“紹介の連鎖”によってビジネスの流れを作り出します。
単に人とつながるだけでなく、「相手と一緒に何を作り出せるか」を意識することで、ネットワークが自然に売上を生む仕組みへと変化するのです。
台湾現地パートナーとの“Win-Win構築”の秘訣
台湾で継続的に成果を出している日本企業には、共通点があります。
それは、「相手を利用しない」姿勢です。
台湾では、取引が一度きりの関係ではなく、“互いに助け合うWin-Winの関係”を重んじます。
たとえば、施工会社にとっても、安定した発注を続ける日本企業は“信頼できる顧客”として扱われ、結果的に優先対応を受けられます。
また、デザイン会社との関係では、共同で新しいプロジェクトを企画するケースもあります。
日本式の品質管理と台湾のスピード感を融合させた「ハイブリッド提案」を共に作ることができれば、両者にとって利益が生まれる。
このような“相互利益型の協業”は、単なるビジネスを超えて、長期的なパートナーシップへ発展します。
「利益を分け合う関係」ではなく、「価値を共に生み出す関係」を目指すことが、台湾で成功する日本企業の共通点です。
信頼ネットワークがブランド価値を高める理由
台湾では「誰と一緒に仕事をしているか」が、その企業の信頼を示す重要な指標になります。
たとえば、「この設計会社は有名百貨店の案件も担当している」「この工事会社は日本の大手チェーンの現場を手掛けている」といった評判は、業界内ですぐに共有されます。
つまり、ネットワークそのものがブランドの一部になるのです。
過去にどんな関係者と協働したかが、新規クライアントの信頼獲得につながります。
さらに、信頼されるパートナーとの連携は、品質保証の証明にもなります。
「A社が関わっているなら安心」という評価が生まれれば、それだけで案件の受注率が上がる。
台湾のビジネスでは、“ブランド=信頼の総和”。
人とのつながりを積み上げるほど、企業としての信用力が増し、自然とブランドが形成されていくのです。
「人脈資産」を見える化し、組織で共有する
多くの日本企業では、台湾で築いた人脈が“担当者個人の財産”になってしまいがちです。
しかし、現地ビジネスを持続的に拡大するには、この人脈を“組織の資産”として共有・活用する仕組みが欠かせません。
具体的には、関係者情報をCRM(顧客管理ツール)や社内データベースにまとめ、案件ごとの関わり方や特徴を記録しておくことです。
「誰とどう関係を築いたか」「どんな対応で信頼を得たか」をチームで共有すれば、担当者が変わってもスムーズに関係を引き継げます。
さらに、台湾では“紹介の文化”があるため、相手のネットワーク構造を理解しておくことも重要です。
「この人を通せば行政ルートが早い」「この会社は優秀な職人チームとつながっている」といった“人脈マップ”を社内で共有することで、全体の営業力が格段に上がります。
人とのつながりを「可視化」し、組織として信頼を継承できる体制を整えることが、次の成長フェーズへの鍵となります。
ネットワークが次の出店チャンスを連れてくる
台湾で成功している日本ブランドの多くは、「現地での再出店が早い」という特徴があります。
その理由は、最初の店舗で築いた信頼ネットワークが、次の案件を自然に生み出しているからです。
たとえば、初店舗の工事を担当した職人やサプライヤーが、新しい立地情報を持ってきたり、別のオーナーを紹介してくれることもあります。
これは、“信頼の連鎖が新しい仕事を呼ぶ”典型的なパターンです。
台湾では、良い評判が口コミで瞬く間に広がります逆に、悪い評判も同じスピードで広まるため、日々の誠実な対応が次のチャンスを左右します。
つまり、ネットワークとは“営業せずに仕事を増やす仕組み”でもあるのです。
一度信頼を得た相手を大切にし、感謝と誠意を持って接し続けること。
その積み重ねが、台湾市場における日本企業の「第二・第三の出店」を支える最大の原動力となります。
まとめ:台湾での成功は「人との信頼をどう育てるか」で決まる
台湾での店舗出店や内装工事を成功させるカギは、設計力でもコスト管理力でもありません。
それらを支えている“目に見えない基盤”──
それが現地ネットワークと信頼関係です。
台湾では日本と比べて人の温度が高く、関係性の濃さがプロジェクトのスピードと品質を左右します。
信頼は“紹介”から始まり、“行動”で育つ
台湾では、「誰から紹介されたか」が最初の信頼を決めます。
紹介者の信用がそのままあなたの信用になるため、最初の接点づくりを丁寧に行うことが重要です。
ただし、紹介はスタート地点にすぎません。
信頼を長続きさせるのは、日々の対応や誠実な行動です。
約束を守り、迅速に連絡を返し、トラブル時に逃げない──
そうした一つ一つの行動が、台湾社会では「信頼の証」として記憶されます。
「関係で動く現場」を理解する
台湾の工事現場では、工程表よりも“関係の温度”が物事を動かします。
書類や契約よりも、「この人のために頑張りたい」と思わせる人間関係こそ、最大のマネジメント力です。
職人・設計者・オーナーの三者関係を円滑に保つには、誰かを責めるのではなく、“一緒に解決する”姿勢を見せることが大切。
台湾の職人たちは、人情に厚く、誠実な相手には全力で応えてくれます。
現場を管理するのではなく、現場と「共に動く」──これが台湾流の現場力です。
サプライヤーと行政は“人の紹介”で動く
資材の手配や行政手続きも、最終的には“誰とつながっているか”でスピードが変わります。
台湾のサプライヤー市場は「顔の見える商売」が基本。
何度も足を運び、誠実に接することで、信頼が積み上がります。
行政も同様で、担当官との関係性が手続きの円滑さを左右します。
そのため、日本企業は現地設計会社や監理者と密に協力し、行政ネットワークを間接的に活用することが有効です。
信頼を得た企業は、次第に「どのルートを通せば早いか」を知り、スピードと確実性で他社をリードできるようになります。
信頼を“企業資産”として継承する
台湾で築いた人脈は、個人のものではなく、企業全体の資産です。
担当者の異動や退職で関係が途切れてしまうと、それまでの努力が水の泡になってしまいます。
だからこそ、人脈を見える化して共有する仕組みが必要です。
誰がどの案件で、どんな関係を築いたのかを社内で記録し、次の担当者が同じ信頼を引き継げる体制を作る。
これこそが、台湾での持続的な成長の礎となります。
ネットワークは“営業しなくても仕事が来る”仕組みになる
台湾市場の面白さは、一度信頼を得ると、次の案件が自然にやってくる点です。
紹介の連鎖、口コミ、リピーター──
これらが強力な営業力となり、企業の成長を支えます。
実際、台湾で複数店舗を展開している日系企業の多くは、初回の現場で誠実に仕事をした結果、“人のつながり”が次の出店チャンスを運んできた例が多いのです。
つまり、ネットワークとは「時間をかけて育てる無形資産」であり、それがやがて“目に見える利益”へと形を変えます。
台湾市場で信頼を築くための黄金ルール
- 焦らず誠実に、まずは人を理解する
- 形式よりも、相手の心に届く対応をする
- 信頼は取引後にこそ深まる
- 紹介されたら、次の紹介を生む行動を心がける
- 人脈を会社の力に変え、組織全体で活かす
台湾で成功している日本企業は例外なく、「人を大切にしてきた会社」です。
その姿勢がブランドを育て、結果的に安定したビジネスへとつながっています。
“人と人が信頼でつながる国・台湾”。
そこでは、数字よりも誠実さ、スピードよりも関係性、効率よりも温度が重視されます。
あなたの会社がこの土地で長く愛される存在になるために──
「信頼という名のネットワーク資産」を、ひとつひとつ丁寧に育てていくこと。
それこそが、台湾での店舗出店・内装設計・施工ビジネスを成功へ導く最強の戦略なのです。