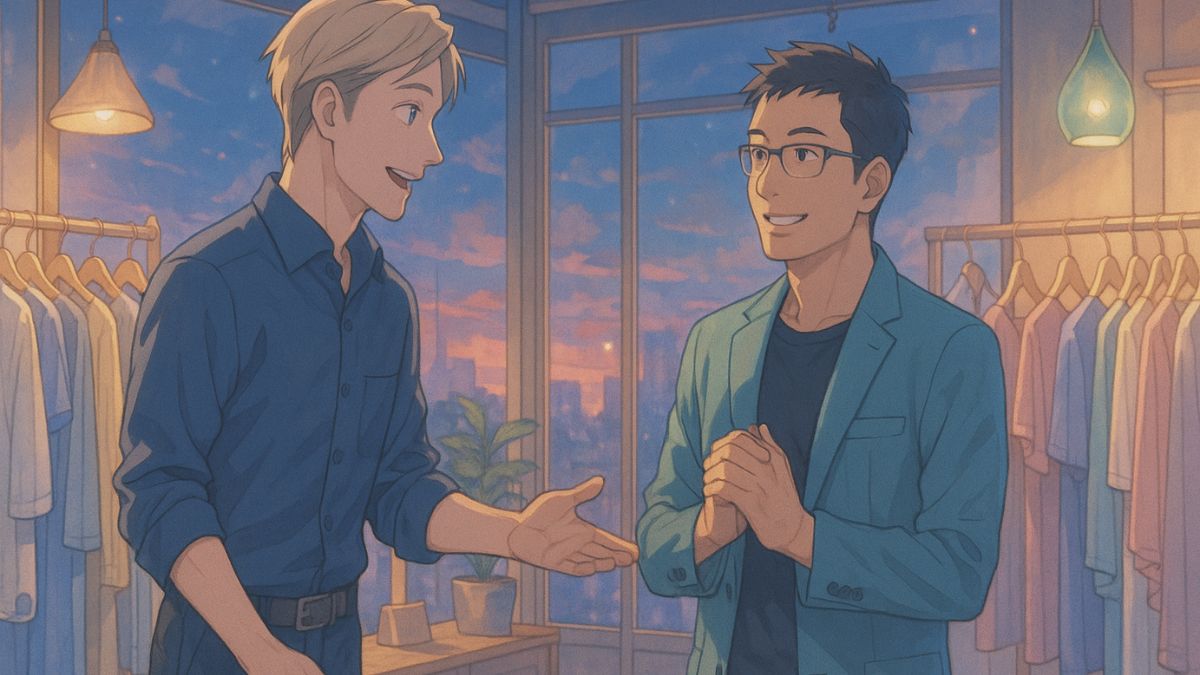台湾での出店を成功させるためには、立地や商品だけでなく「空間づくり」が決定的な差を生みます。
同じアジア圏とはいえ、日本と台湾の人々が“心地よい”と感じる空間デザインの感性は、驚くほど異なります。
照明のトーン、素材の選び方、色彩の好み、さらには「座る高さ」や「空間の距離感」にまで文化的背景が反映されています。
第1章:台湾人が「居心地がいい」と感じる空間とは
― 心理的な“温度”と“距離”のデザイン哲学 ―
台湾で店舗設計を行っていると、日本の空間づくりの「良さ」がそのまま評価されるわけではないことに気づきます。
日本では“静かで整った美しさ”が心地よさを生みますが、台湾ではむしろ“にぎわい”や“温かみ”のある空間に人が集まります。
これは単に文化の違いというよりも、社会的なつながり方そのものが異なることに由来しています。
台湾の人々にとって、店舗は「買い物の場」や「飲食の場」というより、“人と交わる場”としての意味合いが強い。
だからこそ、空間デザインにおいても「人との距離感」や「心理的な温度」が非常に大切になります。
台湾の“社交文化”が生む空間設計のキーワード
台湾社会は、非常に社交的でオープンです。
カフェで一人で過ごしていても、隣の人と自然に会話が生まれたり、スタッフと常連客の距離が驚くほど近かったりします。
この“人との距離の近さ”が、空間デザインにも色濃く反映されています。
例えば、テーブルの間隔。
日本では「プライベート空間の確保」が最優先され隣との間に余裕を取りますが、台湾では逆に「距離が近い方が落ち着く」と感じる人が少なくありません。
人の気配や会話の音が背景にあることが、台湾の人々にとって“安心”のサインなのです。
そのため、台湾の店舗内装設計では、オープンレイアウトやシェア感覚の座席配置が好まれます。
あえて空間を区切らず、視線が交わる設計を採用することで、“賑わいの温度”が生まれます。
「静けさ」より「交流の空気感」。
これが、台湾のデザイン文化の根幹にあります。
明るさと光の質 ── 日本より“やや明るめ”が好まれる理由
台湾の街を歩いてみると、どの店舗も照明が明るいことに気づくはずです。
日本の店舗では、陰影やトーンを活かした「落ち着きのある照明設計」が主流ですが、台湾では“少し明るいほうが良い”という感覚が強くあります。
背景には、台湾の気候と文化があります。
年間を通して湿度が高く、曇りの日が多い台湾では、室内であっても“光”を多く取り入れることで開放感を演出する必要があるのです。
また、台湾の人々は「明るい=清潔」「明るい=繁盛している」という心理的な連想を持ちます。
店舗内装工事の現場では、照度計で数値を測る日本人設計者に対し、台湾のデザイナーは「体感で決める」ことが多い。
照明の演出よりも、“明るく元気”に見えるかどうかが評価基準になります。
そのため、日本の照明計画をそのまま持ち込むと、暗く感じられてしまうケースもあるのです。
素材より雰囲気重視 ── 感触より「映え」
日本では、素材の質感・手触り・経年変化の美しさを重視する傾向があります。
しかし台湾では、“素材そのものの質”よりも“全体の印象”が優先されます。
たとえば、木の質感を再現したメラミンやPVC素材でも、「見た目が良く、写真に映える」ことが重要です。
台湾の消費者はSNSで情報を共有する文化が強く、内装は「撮りたくなる空間」であることが求められます。
そのため、多少人工的であっても、統一感やカラーバランスが取れていれば評価は高いのです。
これは、台湾の室内設計・店舗設計の実務でも顕著に表れています。
素材サンプルよりもCGパースや写真イメージで話が進み、仕上げ感よりも“雰囲気”が重要視されます。
つまり、台湾では「素材の美」ではなく、「空間全体のストーリー」が重視されるのです。
空調・音・香り ── 五感で決まる“居心地の方程式”
台湾で“居心地がいい”とされる店舗には、共通する特徴があります。
それは、空調・音・香りのバランスが絶妙であること。
気候が高温多湿な台湾では、空調の効きが悪いだけで不快度が一気に上がります。
特に飲食店では、湿気対策とニオイ対策の設計が重要で、厨房の排気ルートやエアコン配置の工夫が店舗評価を左右します。
さらに、台湾人は「音」に敏感です。
完全な静寂よりも、心地よいBGMや人の声が混ざる“にぎやかさ”を好みます。
それは、幼い頃から夜市や大家族の生活の中で「音がある=安心」と感じて育った文化的背景によるものです。
そして香り。
台湾の人気カフェやホテルでは、アロマやコーヒーの香りによるブランディングが徹底しています。
香りが空間の印象を決定づけることを台湾のデザイナーたちは本能的に理解しているのです。
「生活感のあるおしゃれ」── 台湾流ミックススタイルの魅力
台湾で流行しているデザインには「整いすぎない魅力」があります。
日本のようにシンメトリーで完璧なバランスを取るより、少し崩した“自然体のデザイン”が心地よいとされます。
これが、台湾の店舗内装の特徴でもある「生活感のあるおしゃれ」です。
たとえば、壁の一部にレンガを残したり、家具をあえてバラバラに配置したり。
無機質すぎず、どこか人の温度を感じる空間が人気を集めています。
台湾人の多くは、「完璧」よりも「親しみやすさ」に価値を置きます。
そのため、設計段階であまりにも“整いすぎた”日本的ミニマリズムを持ち込むと、「冷たい」「落ち着かない」と受け取られてしまうことがあります。
台湾での成功ポイントは、“手づくり感”や“温度感”を残すデザインバランスを意識すること。
第2章:色と光でつくる「台湾で映える」店舗デザイン
― SNS文化と風水感覚が交差する配色術 ―
台湾の店舗内装を手がけていると、「色」と「光」の感覚における日本との違いに驚かされます。
日本では、落ち着いたトーンやナチュラルカラーを中心に、“引き算の美” を追求する傾向があります。
一方、台湾では、
- “明るくて華やか”
- “写真映えする”
- “縁起が良い”
といった要素が重視され、色彩の主張が空間の印象を決定づけると言っても過言ではありません。
また、台湾では「風水(Feng Shui)」の考え方が今も日常の中に息づいており、色や照明にはスピリチュアルな意味が付与されています。
SNS時代の「映える文化」と、古来からの「色の信仰」が共存しているのが、台湾デザインの大きな特徴です。
本章では、台湾の店舗設計における色彩感覚・照明計画・文化的背景を読み解き、日本企業が台湾で魅力的な店舗を作るためのヒントを探ります。
「風水」と「インスタ映え」が共存する不思議な色感覚
台湾の店舗デザインを語る上で避けて通れないのが、「風水(風水學)」です。
住宅だけでなく、店舗設計でも方位や色、照明の配置に“運気”を意識することが少なくありません。
たとえば「赤」は繁栄と活力、「金」は成功と富、「緑」は成長や安定を象徴します。
これらは決して迷信として扱われるのではなく、顧客心理を動かす “縁起デザイン” として自然に受け入れられています。
一方で、若い世代のオーナーやデザイナーの間では、InstagramなどのSNSで「映える」ことが重要な要素です。
結果として、風水由来の色がモダンな配色で再解釈され、伝統とトレンドが共存するデザインが生まれています。
たとえば、淡いベージュをベースに “赤をワンポイントに差す” ── これは「火の気」を取り入れつつ、現代的なバランス感覚でまとめた台湾ならではの色使いです。
台湾のデザインは、合理性よりも「意味」と「感覚」で成立しているのです。
台湾人が好むトーンとは? ── 人気カフェに見る配色傾向
台湾の人気カフェやアパレルショップを観察すると、共通するカラートーンが見えてきます。
それは、「ナチュラルベースにビビッドなアクセント」。
ベースカラーにはベージュやライトグレー、ウッド系のトーンが使われ、そこにターコイズブルー、マスタードイエロー、オレンジなどの“彩度の高い色”が効果的に配置されています。
これは、台湾の人々が明るく楽観的な性格を好む傾向と深く結びついています。
台湾では「元気」「活気」「明るさ」を感じさせる色がポジティブな印象を与えます。
そのため、日本でよく見られる“静寂なグレー一色のカフェ”は、台湾では「地味」「冷たい」と受け取られることがあります。
また、外観においても台湾では色彩表現が豊かです。
通りから見えるファサードに明確なカラーサインを設けることが“集客の要”。
台湾の街並みは広告や看板が多く、視覚情報があふれているため、「色で覚えてもらう」戦略が求められます。
LED照明の使い方──演出と実用のバランス
台湾ではLED照明の進化と普及が非常に早く、店舗内装でも“照明演出”が欠かせません。
しかしその使い方には、文化的な違いがあります。
日本では間接照明や調光で陰影をつくり、“空間の深み”を表現します。
一方台湾では、明るさそのものが店舗の元気さの象徴です。
照明が暗いと「営業していない」「サービスが悪そう」と感じられてしまうこともあります。
特に飲食店では、照明の「色温度」が重要です。
台湾人の多くは、3000K〜4000Kの“やや白っぽい暖色”を好みます。
これにより、清潔感を保ちながらも温かみを演出できるのです。
また、台湾の内装工事現場では、LEDテープライトやスポットライトが大量に使用されます。
照明の配置は“感覚”で決められることも多く、日本のように綿密な照明図を描く習慣はまだ少数派です。
そのため、設計段階で「意図を現場に伝える通訳力」が重要になります。
「赤」「金」「緑」── 台湾で“縁起がいい”色の心理効果
台湾では、特定の色に対して強い感情的な意味づけがあります。
それは商業空間でも明確に意識されています。
- 赤(紅色):祝福・繁栄・幸運を象徴。開業時には必ず赤い布や花が使われます。
- 金(黃色・金色):財運・成功の象徴。ブランドロゴや看板で多用されます。
- 緑(綠色):健康・成長・安心を表す。カフェやオーガニックショップで人気です。
このように、台湾では「色が意味を持つ文化」が生活に根付いています。
デザインの目的が「美しさ」だけでなく、「運を呼び込むこと」まで含まれているのです。
一方で、黒や灰色は慎重に扱う必要があります。
高級感を演出する色ではありますが、場合によっては「不吉」「重い」と受け取られることも。
そのため、日本的な“黒の美学”を導入する際は、金属や木の素材と組み合わせて柔らかく見せる工夫が求められます。
日本的ミニマルデザインを“温かく見せる”台湾的光の演出法
台湾で日本的なミニマルデザインを展開する際、最も気をつけるべきは「冷たさの回避」です。
直線的で無彩色の空間は、台湾人にとっては“洗練”よりも“寂しさ”を感じさせることがあります。
そこで鍵となるのが、「光の温度」と「陰影のやわらかさ」です。
ミニマル空間でも、間接照明にわずかに暖色を混ぜるだけで印象が大きく変わります。
また、照明を壁や天井に反射させることで “柔らかい光の膜” をつくると、冷たさが消え、包み込むような空間になります。
台湾の人々は、光の “やさしさ” に敏感です。
だからこそ、日本の照明技術を生かしながら、台湾の感性に合う「光の温度」を再設計することが成功のポイントになります。
つまり、「引き算のデザイン」をそのまま持ち込むのではなく、“温度のあるミニマル”に変換すること。
それが、台湾の内装設計・店舗設計で本当に受け入れられるデザイン手法です。
第3章:素材とディテールの“こだわり”の違い
― 台湾市場で通用する質感と施工精度を見極める ―
日本の設計・施工の世界では、素材選びとディテールの精度が品質の象徴です。
しかし台湾で店舗設計や内装工事を手がけてみると、「細部の美しさ」よりも「仕上がりの印象」や「スピード」が評価される傾向が強いことに気づきます。
たとえば、日本では「この目地が1ミリずれている」と指摘が入るような場面でも、台湾では「全体が良ければ問題ない」という判断が多い。
これは単なる施工精度の差ではなく、文化・気候・商習慣の違いから生まれた価値観の違いなのです。
「本物素材」より「再現素材」が選ばれる理由
日本の設計者がこだわる天然素材 ── 無垢材、大谷石、左官仕上げなどは、台湾ではコストや施工性の面から敬遠されることがあります。
代わりに選ばれるのが、メラミン化粧板・PVCシート・人工大理石などの再現素材です。
理由は明快です。
台湾は高温多湿の気候のため、木材や漆喰などの天然素材が膨張・変色・カビの原因になりやすい。
また、店舗のリース契約が短期で更新されるケースも多く、「長期耐用」より「短期コスト」が優先される傾向があります。
つまり、“リアルより実用”の選択です。
表面の質感よりも、施工のしやすさ・清掃のしやすさ・交換のしやすさが重視されます。
そのため、見た目は自然素材に見えても、実際は軽量で加工しやすい工業素材で仕上げるケースが圧倒的に多いのです。
この感覚を理解しておかないと「日本品質」を求めすぎて見積りが膨らみ、発注に至らないこともあります。
素材の“本物らしさ”より、“台湾らしい合理性” を踏まえた提案が求められます。
台湾の湿度と素材劣化 ── 設計段階でのリスク回避策
台湾の内装工事現場で最も注意すべきは、湿度による素材劣化です。
特に梅雨時期(5月〜6月)は湿度が90%を超えることもあり、施工中の木材やクロスが膨張・剥離することがあります。
そのため、設計段階から「湿気を逃がす」仕組みが必要です。
たとえば、壁面に空気層を設けたり、化粧板の裏に通気孔を確保したりすることで、仕上げ材の寿命を延ばすことができます。
また、床材も無垢フローリングではなく、ビニルタイル(SPC、LVT)の方がメンテナンス性・寸法安定性で優れています。
一方で、日本的な左官仕上げや珪藻土は、台湾では「湿気を吸いすぎる」「カビやすい」との理由で避けられがちです。
素材の美しさを優先するなら、湿度対策をセットで設計することが大前提になります。
台湾では、「デザインが美しい」より「維持が楽」「壊れにくい」ことが、結果的に “いい設計” として評価されるのです。
職人の精度よりスピード重視? 台湾施工現場のリアル
台湾の内装工事現場に入ると、日本との最も大きな違いを感じるのが“時間の感覚”です。
日本では「納期=完成品質」、台湾では「納期=スピード重視」。
現場監督の指示も「明日までに仕上げて」と言えば本当に仕上がるのですが、よく見ると細部の精度には差があります。
これは台湾の工事現場が「多現場・短工期」を前提としているため。職人たちは複数の現場を掛け持ちしており、1つの現場に集中できる時間が限られているのです。
また、台湾では「監督」という立場が日本ほど強く機能していません。
各職人が現場で臨機応変に判断しながら進めるため、“現場力”は高いが、仕上げ精度は揺らぎやすいという特徴があります。
したがって、日本式の図面や仕様書をそのまま渡すだけでは不十分です。
「どの部分を優先して精度を上げるのか」「どの部分は現場対応で良いのか」を明確に伝えることが重要です。
台湾の現場では、100%完璧を求めるより現場で柔軟に修正できる余地を残す設計のほうが実際的です。
日本品質を保ちながらコストダウンする工夫
台湾の内装単価は日本より安いと言われますが、実際には「同品質」を求めると大きな差はありません。
むしろ、日本品質を現地価格で再現するための工夫が問われます。
ポイントは、
- 仕上げ材を日本から輸入せず、台湾市場で入手できる代替品を見極めること
- 現場での再加工を避け、工場で事前に仕上げたユニットを使うこと
- 重要な部分だけを「日本式精度」に絞り込むこと
です。
たとえば、カウンターの天板だけ日本製人工大理石を採用し、下地やバックヤード部分は現地材を使用する。
こうした “ハイブリッド品質” がコストとクオリティのバランスを取る鍵になります。
また、台湾の工事会社は「材料支給(甲供材)」に柔軟に対応してくれるケースも多い。
仕上げの質を守るために、日本側で重要材料だけを供給するスキームを組むのも一つの方法です。
“ローカル資材を使った日本的空間” の成功事例
台湾で成功している日系店舗の多くは、現地資材を上手にアレンジしています。
たとえば、台北のある高級カフェでは、内装の壁材に台湾産の石灰モルタルを使用し、日本的ミニマルを現地素材で表現しています。
また、日本の飲食チェーンでは、台湾の竹やラタン素材を照明や壁パネルに取り入れることで、温かみと地域性を両立させています。
このように、“ローカル資材で日本的世界観を構築する” 発想は、台湾の設計会社にも評価されています。
それは単なるコスト削減ではなく文化融合のデザイン戦略としての価値があるのです。
日本側が素材の背景や施工意図を丁寧に共有し、台湾の職人が現場で創意工夫を加える。
この「共創型の現場づくり」こそが、台湾で成功する店舗デザインの鍵となります。
第4章:台湾人オーナーが「いいね!」と感じるデザイン提案
― 会話・文化・価値観の翻訳が成功を左右する ―
台湾で店舗設計や内装工事を進める際、日本人設計者が最も苦労するのが「提案の伝わり方」です。
図面もプレゼン資料も完璧に準備したのに、台湾人オーナーの反応がいまひとつ……
その原因は、デザインの内容そのものではなく “伝え方” や “関係づくりのプロセス” にあることが多いのです。
台湾では、ビジネスの出発点が「人間関係」です。
「信頼できる人」からの提案であれば、内容が多少荒削りでも採用される。
逆に、どんなに優れたデザインでも、距離を感じる相手の案は通らない。
この章では、台湾人オーナーに「いいね!」と思ってもらえるデザイン提案の進め方を、会話・文化・心理・実務の4つの側面から具体的に解説します。
台湾のオーナーは“人間関係”を最重視する
日本では、まず「内容」や「実績」で評価されます。
一方、台湾では「誰が言うか」が先に問われます。
つまり、オーナーは “信頼できる人”の提案を採用する文化を持っています。
打ち合わせの初回から、いきなり図面や見積もりの話に入るのはNGです。
まずは世間話から始め、趣味や家族、食の話などを交えながら、会話の空気を温めることが大切です。
「人を知ってから、仕事の話をする」── これは台湾ビジネスの基本マナーともいえます。
実際、台湾の店舗オーナーは「この人と一緒に作りたい」と感じた瞬間に発注を決めることが多い。
したがって、デザインの良し悪しよりも、信頼と共感を得ることが先決です。
誠実さとフレンドリーさの両立が、最強の武器になります。
「数字」より「感情」── 提案書の作り方に違いが出る理由
日本の提案資料は、ロジカルで数値的。
坪単価・工期・メンテナンス性など、データで納得させる構成が多いですが、台湾ではそれが必ずしも響きません。
台湾のオーナーは、「この空間で自分がどう感じるか」「お客様がどんな気持ちになるか」という感情軸で判断する傾向があります。
そのため、デザインプレゼンでは、論理よりも感覚で伝える構成が有効です。
たとえば、
- 3Dパースで空間の雰囲気を見せる
- BGMや照明の動画を使って体感的にプレゼンする
- 「この席に座ったお客様が笑顔になるシーン」を言葉で描く
こうした方法が、数値データよりも強い説得力を持ちます。
台湾のプレゼン文化は、“共感を呼ぶストーリーテリング” が中心。
「理屈で納得」より、「心で共感」が決め手です。
モデル写真の選び方で伝わり方が変わる
日本のデザイン事務所が台湾でよく陥る誤解に「日本の施工事例をそのまま見せれば好印象を持たれる」というものがあります。
しかし実際には、あまりに日本的で静かなデザイン写真は「遠い世界の話」として受け止められてしまうことが多いのです。
台湾のオーナーに響く写真は、“生活感” や “人の温かみ” が感じられるものです。
たとえば、照明の明るい空間、彩度のあるインテリア、笑顔のスタッフやお客様が写っている写真など。
「自分の店もこうなれる」と想像できるリアリティが大事です。
そのため、プレゼン資料では台湾の既存店舗や街並みに近い雰囲気の写真を混ぜることをおすすめします。
また、現地の施工例を参考にすることで、「台湾でも実現可能なデザイン」として受け入れられやすくなります。
つまり、写真選びは「文化翻訳」。
どんなに洗練されたデザインでも、伝え方を間違えれば伝わりません。
“台湾人の目線で見てどう映るか” を常に意識することが重要です。
台湾の “現場での修正文化” を前提にした設計姿勢
台湾の店舗づくりで驚かされるのが、「現場での変更の多さ」です。
施工途中でオーナーが現場を訪れ、「ここ、もう少し明るくしたい」「棚の位置を変えたい」といった修正指示を出すのは日常茶飯事。
日本では変更を嫌う傾向がありますが、台湾ではそれが「関与している証拠」とみなされます。
オーナーにとって “現場で考える” ことは、むしろデザインへの参加行為なのです。
そのため、日本式の「事前確定・完全図面主義」は、台湾では現実的ではありません。
この文化に合わせるには、設計段階で “変更前提の余白” を残すことが大切です。
たとえば、照明計画を変更しやすいダクトレールにしておく、壁面装飾を後付けできる設計にしておくなど。
現場での微調整を柔軟に受け入れる姿勢が、「融通が利く設計者」として信頼を生みます。
台湾では、完璧な図面よりも “現場力” を持つ設計者 が評価されるのです。
「一緒に作る」感覚を共有することで信頼が生まれる
台湾での店舗設計・内装工事の成功は、最終的に「チームワーク」で決まります。
オーナー・設計者・施工会社が “共に作る” という感覚を持つことが重要です。
日本では設計と施工の関係が分業的であり、役割分担が明確ですが、台湾ではプロジェクトの進行中に全員が意見を出し合うことが一般的です。
この「混ざり合う現場文化」を理解し、尊重することで、信頼関係が深まります。
たとえば、オーナーがDIY的な提案をしてきたときに、「それは難しい」と否定するより、「それも面白いですね、こうすれば実現できます」と答える。
この一言で、距離が一気に縮まります。
台湾の現場では、上下関係よりも “仲間意識” が重要です。
設計者がチームの一員として関わる姿勢を見せることで、オーナーの心が動き、結果的にスムーズな工事進行と高い満足度につながります。
台湾で「いいね!」と言われるデザイン提案とは、図面や資料の完成度ではなく、“共感と参加を生むプロセス” にこそ価値があるのです。
第5章:台湾で成功する店舗デザインの条件
― 日台の強みを融合させた「共創型デザイン」の時代へ ―
台湾で数多くの店舗内装設計・施工を手がけてきて、強く感じることがあります。
それは、成功する店舗には「日本式」でも「台湾式」でもない、“第三の空間” が存在するということです。
日本の強みは、緻密な計画性と細部まで妥協しない完成度。
台湾の強みは、柔軟な発想とスピード感、そして人との関係性を大切にする温かさ。
両者が融合したとき、初めて台湾市場に本当に受け入れられる空間が生まれます。
それは単なる設計ノウハウではなく、文化の橋渡しとしてのデザイン哲学でもあります。
「日本式」でも「台湾ローカル」でもない第三の空間へ
台湾で日本企業が出店する際、よくある失敗が「日本の店舗をそのまま再現してしまう」ことです。
確かに日本的な清潔感やミニマルデザインは一見好印象ですが、現地の人々から見ると「距離を感じる」「落ち着かない」と受け取られることがあります。
成功している日系ブランドは、台湾の生活文化に“溶け込む”工夫をしています。
たとえば、照明の色温度を少し上げて温かみを加えたり、壁面に台湾産の素材を取り入れたり。
デザインの方向性は日本らしくても、「空気感」は台湾に合わせて調整されているのです。
つまり、「日本式の完成度 × 台湾的な温度」= 第三の空間。
この融合デザインこそが、台湾で長く愛される店舗をつくるための出発点です。
台湾スタッフとの協業が生む“デザインの余白”
台湾の設計会社や施工会社と仕事をするとき、重要なのは “任せすぎないこと” と “指示しすぎないこと” のバランスです。
日本式の完全管理では、現場が窮屈になり、柔軟な発想が生まれません。
一方で、任せきりではクオリティが不安定になります。
最も良いのは、“余白を持った協業” です。
日本側が基本設計とデザインの方向性を固め、台湾側が現場判断と素材調整を担う。
その間に「調整のための余白」があると、双方の良さが活かされます。
台湾の現場では、デザイナーと職人が直接対話しながら改良を重ねていくスタイルが一般的です。
この即興的なやり取りの中から、新しい表現が生まれることも多い。
「現場での発見をデザインに還元する力」── それが台湾デザインの最大の魅力です。
施工会社の選定がデザインを左右する
台湾の内装業界は企業の規模も実力もピンからキリまであります。
見積金額だけで選ぶと、仕上がりの差が大きく出るのが現実です。
特に店舗のように工期が短く、予算が限られている場合、「設計意図を理解できる施工会社」を選ぶことが最も重要です。
その見極めポイントは3つあります。
- 過去の施工写真を見たときに、仕上がりの“清潔感”があるか。
- 担当者が設計図面を読み込み、質疑を多く出してくるか。
- 修正対応に対して前向きな姿勢を持っているか。
台湾では「仕事が早い」よりも「意思疎通が早い」会社を選ぶべきです。
現場監督が日本式の意図を理解し、柔軟に調整してくれる会社であれば、仕上がりの精度が格段に上がります。
また、設計者自身が定期的に現場に足を運び、“顔を見せる設計” を意識することも大切です。
台湾では、関係性が品質を支えるのです。
成功事例に見る“現場調整力”の重要性
ある日系カフェチェーンの台湾出店では、工事中に大きな課題が発生しました。
輸入予定だった壁材が港のトラブルで届かず、開店スケジュールが危機に陥ったのです。
そのとき台湾の施工チームが即座に提案したのが、「現地で手配できる類似タイルを使い、目地色で質感を近づける」方法でした。
結果として、完成した店舗はむしろ現地の街並みに馴染み、「台湾限定の温かい雰囲気」として好評を得ました。
このように、“現場調整力”こそが台湾市場での武器です。
日本式の完璧主義を柔軟に手放し、「現場の創意工夫を活かす設計」に転換することで、日台協業のチームはより強くなります。
図面通りに仕上げることがゴールではなく、「現場で最良の解を導き出すこと」こそが真の完成 ── それが、台湾の店舗デザインにおけるリアルな成功条件です。
台湾出店を「ブランド体験の進化」として捉える視点
台湾出店を単なる海外展開と考えるのはもったいない。
むしろ、それはブランド体験を再構築する絶好の機会です。
台湾の人々は、日本ブランドに対して高い信頼を持っていますが、同時に「台湾らしさ」を求めます。
たとえば、メニューや什器、空間演出の中に台湾文化の要素を少し加えることで、“日台融合のブランド体験” を生み出せるのです。
実際に、ある日本発のスイーツブランドは、台湾限定で「蓮花」をモチーフにしたインテリアを採用し、SNSで「台湾らしくてかわいい!」と話題になりました。
ブランドの一貫性を保ちながら、ローカル文化を取り入れる姿勢が支持されたのです。
これからの時代、出店は拡大ではなく「深化」。
台湾での店舗設計・内装工事は、ブランドのアイデンティティをより豊かにする“進化の実験場”になり得ます。
まとめ:台湾で “受ける” デザインは、「文化を翻訳する力」から生まれる
台湾で店舗をつくるということは、単に図面を引いて空間を仕上げることではありません。
それは、文化を翻訳する仕事です。
日本の「美意識」と台湾の「生活感覚」。
この二つの間にある微妙な温度差を読み取り、調整し、融合させていく。
そのプロセスこそが、台湾で成功する店舗デザインの真髄なのです。
台湾人が心地よいと感じる “温度のある空間”
第1章で見たように、台湾の人々が「居心地がいい」と感じる空間には、人の気配や温度があります。
静寂よりもにぎわい、孤独よりも共感。
人と人が近づく空気をデザインすることが、台湾の店舗設計の第一歩です。
光はやや明るめに、距離はやや近めに。
日本の“静かな美”を、そのまま輸出してもうまくいかないのは、この「空間が担う役割」そのものが文化的に違うからです。
「風水」と「映え」が共存する台湾の色と光
第2章で解説したように、台湾では色や光に“意味”があります。
風水の思想とSNSの文化が同居し、赤・金・緑といった色に幸運や繁栄の願いが込められています。
同時に、Instagramで「映える」ことも現代のデザイン評価の大きな軸。
つまり、台湾のデザインは理屈ではなく感覚で動く。
「縁起がいい」と「見栄えがいい」が共鳴するデザインが、“売れる空間”をつくるのです。
日本的ミニマルをそのまま持ち込むのではなく、「温度を感じるミニマル」に翻訳して見せる──それがプロの仕事です。
台湾の素材文化に寄り添う設計視点
第3章で扱った素材と精度の違い。
台湾では、天然素材よりも再現素材、手づくりの精度よりもスピードと実用性が優先される現場が多い。
この背景には、湿度、工期、コスト、そして「実用美」を重んじる文化があります。
日本式の“完璧さ”に固執するのではなく、「どこを精緻に」「どこを柔軟に」仕上げるかを見極めるバランス感覚が求められます。
その判断力こそ、台湾で信頼される設計者・現場監督の証です。
また、現地資材を上手に使いながら日本らしい空気を表現する「ローカル×日本」のアプローチは、コストを抑えながらもブランド性を高める有効な戦略です。
「伝える」より「共に作る」プレゼン文化
第4章では、台湾人オーナーとのコミュニケーションの本質を掘り下げました。
台湾では、「人間関係」からすべてが始まります。
最初に信頼を築ければ、提案は自然に通ります。
提案は論理ではなく感情、数字ではなくストーリー。
図面よりも「どんな気持ちになれる空間か」を伝えることが、台湾人オーナーに“いいね!”と言ってもらえる最大のポイントです。
さらに、現場での変更や意見を受け入れる「余白」を設計に残すこと。
この柔軟さが、“一緒に作っている”という共感を生み、信頼関係を深める土台になります。
台湾で成功する店舗は、日台の融合から生まれる
そして第5章では、最終的な結論として、台湾で成功している店舗には共通する“デザイン哲学”があることを確認しました。
それは──
日本式の精密さ × 台湾的な柔軟さ × 共感を生む関係性
この3つが交わったとき、店舗は「外国ブランド」ではなく「台湾に根づいた文化体験」になります。
台湾出店を単なる拡張と考えるのではなく、ブランドが新しい文化と出会い、進化するプロジェクトとして捉える。
その視点こそが、これからの日台ビジネスの本質です。
おわりに:信頼は図面の外で育つ
台湾での店舗づくりを成功させる最大の鍵は、図面の完成度でも見積の安さでもありません。
それは、“人と人の信頼”という目に見えないデザインです。
台湾の設計会社や施工会社は、日本企業の丁寧な姿勢を高く評価しています。
一方で、彼らの柔軟さと現場対応力は、日本の設計者に新しい刺激を与えてくれます。
この相互尊重があってこそ、良い空間が生まれます。
台湾市場で「受ける店舗デザイン」を生み出すとは、日本の美学を守りながら、台湾の文化に敬意を払い、共に歩むこと。
その積み重ねが、やがて日台の信頼を深め、両国のデザイン文化をより豊かにしていくでしょう。
もしあなたが今、台湾での出店を検討しているなら、最初に選ぶべきは「設計会社」ではなく、「共に考えてくれる現地パートナー」です。
図面の外にある「人とのつながり」を大切にすること。
それが、台湾の店舗づくりで最も価値ある“デザイン”です。