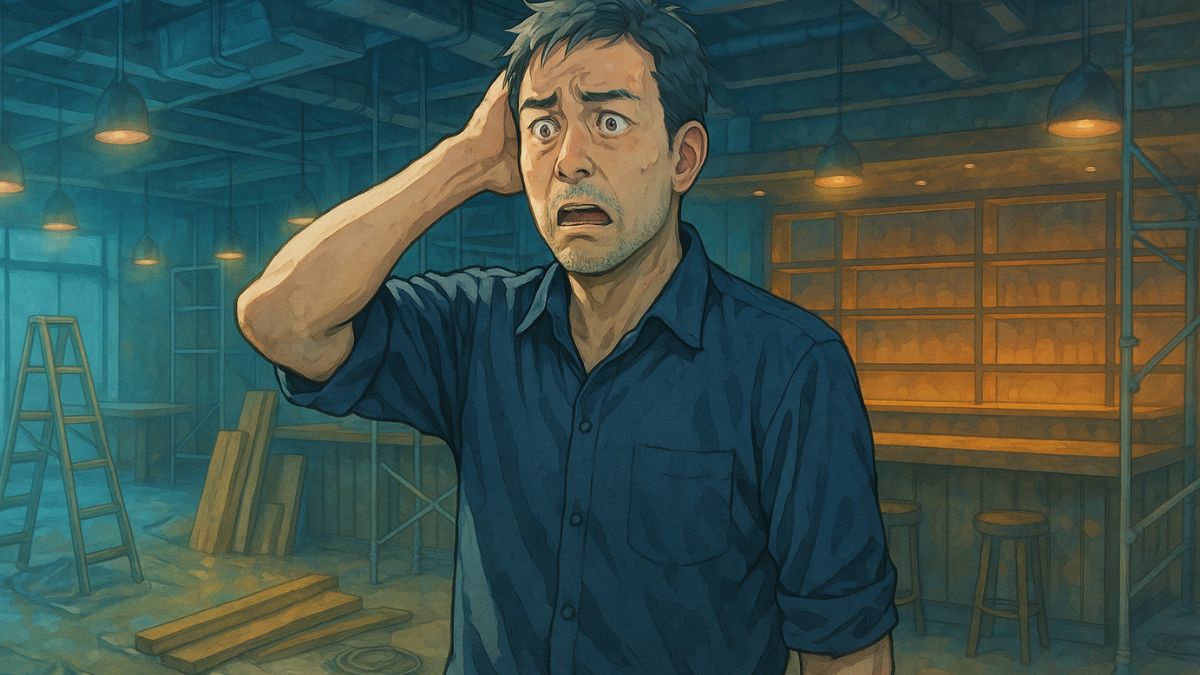日本の常識が通じない。
それが台湾の内装現場です。
図面を描いたのに違う仕上がり、仕上げ精度のズレ、予期せぬ工程遅延、法規不適合、そして伝わらない意図。
本記事では、日台の店舗設計・内装工事の現場を知り尽くした筆者が、日本企業が台湾出店で犯しやすい“5つの設計ミス”を解説します。
文化や現場の違いを超え、台湾の設計会社と真に信頼関係を築くための実践的ヒントをお届けします。
第1章:図面が現場で“通じない”──日本式設計の盲点
日本企業が台湾で店舗設計を進める際に、最初にぶつかる壁が「図面が現場に通じない」という問題です。
- 「しっかり図面を描いたのに、仕上がりが全然違う」
- 「指示通りの納まりになっていない」
こうしたトラブルは、決して一部の特殊なケースではなく、台湾の店舗設計・内装工事の現場では非常に頻繁に起こります。
原因は単純ではありません。
図面の描き方の違い、文化の違い、施工者の理解力の差、そして“誰が判断するのか”という責任の所在の曖昧さ。
日本のように「図面通りに施工する」ことが当たり前の文化は、台湾では必ずしも成立しません。
むしろ台湾では、「図面は参考、現場で最適を考える」という柔軟な姿勢が根づいているのです。
図面よりも“口頭確認”が優先される台湾現場のリアル
台湾の内装現場では、図面よりも「現場での会話」が優先されることが少なくありません。
つまり、設計図に細かく寸法や仕様を記してあっても、実際の施工時には「現場で相談して決める」文化が根づいています。
その背景には、台湾では設計者と施工者の間の階層的な関係が日本ほど明確ではなく、職人の裁量が大きいという事情があります。
「この材料は湿度に弱いから、こっちの方法でやった方がいいよ」といった判断を、現場のベテラン職人が即興的に下すケースが多いのです。
日本ではそれを「勝手に変えた」と捉えがちですが、台湾では「プロとしての提案」として受け止められています。
つまり、台湾では“図面より現場判断”が尊重される文化があり、ここを理解しないと、いくら図面を緻密に描いても思い通りの空間にはなりません。
「1/50図面」が細かすぎる? 台湾職人が読む“感覚の図面”
日本では、1/50図面や1/20詳細図が当然のように使われます。
しかし台湾では、図面があまりにも詳細だと、逆に混乱を招くことがあります。
台湾の職人の多くは、図面を「方向性を示すもの」として認識しており、細かい寸法指示よりも「仕上がりイメージ」を重視します。
たとえばカウンターのコーナーR寸法を“10mm”と指示しても、実際には「大体このくらい」で処理されることが珍しくありません。
また、台湾の図面は全体的にラフで、「どのレベルで施工者が判断するのか」が曖昧なことも多いです。
結果として、日本側が意図する「精度の高い設計」をそのまま適用すると、職人側が“理解不能”となり、最終的に「感覚で合わせた」施工になってしまうのです。
したがって、日本企業が台湾で設計を依頼する場合、図面の細かさよりも「理解されやすい図面」を意識することが重要です。
台湾側の理解度を踏まえた“図面の翻訳”が、プロジェクト成功の鍵となります。
設計者と施工者の役割が曖昧な台湾の文化背景
日本では、設計者は設計者、施工者は施工者という明確な役割分担があります。
しかし台湾では、設計会社が施工管理まで行う場合も多く、また工事会社側が「設計提案」を行うことも珍しくありません。
この“設計と施工の境界が曖昧”という文化こそ、図面が通じない最大の要因のひとつです。
台湾では、「図面はあくまで設計者の提案であり、最終判断は現場が行う」という意識が存在します。
特に飲食店舗や物販店舗のようなスピード重視の案件では、「図面通りよりも早くオープンできること」が優先されるのです。
日本企業がこの点を理解せず、「図面通りじゃない」と抗議しても、台湾側から見れば「柔軟に対応したのに」と受け止められる場合が多いです。
つまり、日本式の“設計主導”ではなく、台湾式の“協働的現場判断”という文化を理解した上での対応が求められます。
「仕上表」を理解してもらえないのはなぜか
日本では、壁紙や床材、塗装色などを一覧化した「仕上表(仕上げ表)」が非常に重要です。
しかし台湾では、この仕上表がそのままでは機能しないことが多々あります。
理由は、台湾の職人や施工会社が使う材料が異なり、同じメーカーや品番が流通していないからです。
「日本のサンゲツ品番で指定したのに、現地では別の素材に置き換えられていた」というのは、非常によくある話です。
また、台湾では“サンプル現物”を見て判断する文化が強く、「表上の指定」よりも“手で触って確認する”ことを重視します。
つまり、文字情報よりも“実物確認”が重要であり、仕上表を出すだけでは意図は伝わりません。
日本企業が台湾で設計する際は、「仕上表+サンプルボード+現物写真」で伝えることが有効です。
設計図面の補足として、素材の質感を共有する仕組みを整えることが、完成後の満足度を大きく左右します。
日本式の図面精度を台湾で活かすための実践策
では、日本式の精密な設計を台湾現場で活かすにはどうすればいいのでしょうか。
答えは、「正確さを求める前に、理解の共有を徹底する」ことです。
まず、図面を提出する前に、台湾側の設計担当や施工責任者と「どの部分を重視してもらいたいか」を共有します。
全ての図面を完璧に理解してもらうのではなく、“重要ポイントを絞る”ことがポイントです。
また、図面の注釈に「この寸法は厳守」「この部分は現場判断可」といった明確な区別を記載しておくことで、誤解を減らすことができます。
台湾では「全部重要」と書かれても、どこに優先順位があるのか分からないため、結局“感覚施工”になってしまうのです。
さらに、設計者自身が現場に足を運び、現場監督・職人と直接コミュニケーションを取ること。
台湾の現場では、図面よりも「人」が優先されます。
設計者が顔を出すだけで、図面の理解度が一気に上がることも多いのです。
第2章:素材と施工精度の思い違い──“仕上がり感”のズレ
台湾で内装工事を経験した日本企業の多くが、竣工後に最初に感じる違和感は「仕上がり感」です。
「同じ素材を使ったのに、日本の店舗のような上質さが出ない」「木目の流れや角の処理が雑に見える」。
このような“感覚的な違い”は、実は偶然ではなく、文化・気候・施工環境の複合的な差から生じています。
台湾の内装工事は、日本よりもスピード重視で、全体を早く仕上げることを優先する傾向があります。
そのため、細部の処理や素材の扱い方が日本式と異なり、結果として「同じ材料でも見え方が違う」という現象が起こるのです。
さらに、台湾の高温多湿な環境では、素材そのものの性質や経年変化のスピードも異なります。
台湾では“完璧すぎる”仕上げは逆に不自然?
日本では、ミリ単位の精度で納まりを追求し、角の処理や塗装のムラひとつにも厳しい目が向けられます。
しかし台湾では、「完璧すぎる仕上げ」は必ずしも歓迎されません。
台湾の店舗やオフィスでは、仕上がりよりも「活気」「使いやすさ」「雰囲気」を重視する傾向があります。
たとえば、壁の小さな歪みや家具の微妙な色差は「味」として受け入れられる場合が多く、「すぐ営業できる」ことが最優先になるのです。
この文化的背景の違いが、仕上げ精度の考え方に大きな影響を与えています。
つまり、日本では“完成形”を目指すのに対し、台湾では“稼働できる状態”をゴールとする。
設計段階でこの価値観の違いを共有しないと、施工側との間に不満や誤解が生じやすくなります。
湿度と温度が左右する内装材の寿命と質感
台湾の内装設計で見落とされがちな要素が、「湿度と気温の影響」です。
台北や高雄では、年間を通して湿度が高く、木材や塗装材、接着剤にとっては厳しい環境となります。
日本の設計者が好む無垢材や突板仕上げは、台湾では膨張や反り、接着の剥離を起こすことが少なくありません。
さらに、空調設備の運転時間が短い店舗では、温度差による結露やカビが生じやすく、美しい木目がわずか半年で曇ってしまうケースもあります。
したがって、台湾で設計を行う際には、素材の「耐湿性」と「保守のしやすさ」を最優先に考える必要があります。
特に木材・塗装・クロス・床材は、気候条件に応じた仕様変更を行うことが成功の鍵です。
素材の選択段階で現地業者の意見を取り入れることで、想定外の劣化を防ぐことができます。
「同じメーカーの材料なのに違う」台湾市場の輸入事情
「日本と同じメーカーの素材を指定したのに、仕上がりが違う」というケースも多くあります。
その理由は、台湾国内で流通している同ブランド品が、実は仕様や生産国が異なることにあります。
たとえば、日本製クロスメーカーの商品でも、台湾で販売されているのは東南アジア製OEMだったり、ローカル代理店が独自に仕入れた“似た品番”であったりします。
結果として、質感・厚み・光沢・接着力が微妙に異なり、完成後の印象が変わってしまうのです。
また、輸入建材の場合、関税や輸送コストの関係で「同じ製品を使うと日本の2〜3倍のコストになる」ことも珍しくありません。
そのため、現場ではコストダウンを理由に“現地代替材”が使われるケースが多く、それが仕上がり感の差につながります。
つまり、台湾の店舗内装では、素材指定=同一品質保証ではないのです。
日本の図面指定をそのまま持ち込むのではなく、
「現地調達可能な同等品」を設計段階で確認する仕組みを整えることが求められます。
仕上がりを左右する職人の“経験値の幅”
台湾の施工職人の技術レベルは幅が広く、熟練者と初心者の差が非常に大きいのが現実です。
熟練の木工職人であれば、日本のディテールを理解し高精度で仕上げることができますが、短期契約の職人や臨時雇用の作業員が多い現場では、再現性に大きなばらつきが出ます。
この背景には、台湾では職人が「会社所属」ではなく「個人請負」で動くケースが多いことがあります。
そのため、同じ現場でも日ごとにメンバーが入れ替わり、昨日指示した内容が翌日には伝わっていないということも起こり得ます。
日本企業としては、こうした現場事情を前提に“管理強化”を図る必要があります。
図面や仕様書だけに頼らず、「確認・報告・写真共有」を習慣化することで品質を安定させることができます。
また、台湾では「信頼関係を築いた職人」に仕事を依頼する慣習が強いため、
一度良いチームを見つけたら、継続的に同じ人材に依頼するのが成功のコツです。
素材感のズレを最小限に抑えるための監理ポイント
台湾で日本クオリティを再現するには、施工監理の段階で素材の見え方・手触りの確認を徹底する必要があります。
「指定どおりの材料を使ったか」だけでなく、「その材料が現場でどう見えるか」を実際にチェックすることが重要です。
たとえば、照明の色温度が異なるだけでも、木目や塗装色の印象は大きく変わります。
また、台湾では塗装業者が塗料を現場で希釈して使用することも多く、日本で想定していた発色や艶感が出ないこともあります。
そのため、監理者は「施工中に現物を確認」することを徹底し、「一度塗ってみて確認する」「一部を貼って見てから判断する」といった現場調整を取り入れるとよいでしょう。
加えて、完成後の引き渡し前に、素材の保守・清掃・メンテナンス方法をオーナーに伝えることも大切です。
台湾の高湿度環境では、仕上げを長持ちさせるための知識共有が不可欠です。
こうした「監理と教育」を通じて、日本式の精度を台湾の現場に根づかせることができます。
第3章:スケジュールの読み違い──“納期意識”が違いすぎる
台湾で店舗設計・内装工事を進める際、多くの日本企業が最も頭を抱えるのが「スケジュールのズレ」です。
- 「着工日を決めたのに工事が始まらない」
- 「材料が届かず工期が延びる」
- 「オープン日が迫っても仕上がらない」
こうしたトラブルは、台湾現場では決して珍しくありません。
その原因を単に“台湾はルーズだから”と片づけてしまうのは危険です。
実際には、工程管理の考え方、現場の仕組み、人の働き方の違いが深く関係しています。
日本では工程表が「契約の一部」として厳密に運用されますが、台湾では「目安」として扱われるのが一般的です。
また、台湾では職人が複数の現場を掛け持ちするのが当たり前で、スケジュールの前提がそもそも異なるのです。
この章では、台湾の現場における“時間感覚”の実情を掘り下げながら、日本企業が誤解しやすいポイントと、スケジュール遅延を防ぐための実践策を紹介します。
台湾の現場に“監督”が不在という現実
日本の内装現場では、施工会社の現場監督が常駐し、職人の動きを管理します。
一方、台湾の多くの現場には「監督」という役職が存在しません。
現場の調整は、設計者や工事会社の代表が兼任するケースが多く、日々の作業を細かく管理する人がいないのです。
つまり、台湾では「現場を誰が仕切るのか」が曖昧なまま、工事が進んでいくことも珍しくありません。
特に複数業者が関わる現場では、調整役がいないため、作業順序の混乱や納期の遅れが頻発します。
この構造を理解せずに日本式の工程管理を持ち込むと、「なぜ誰も進捗を報告してこないのか?」という事態に陥ります。
台湾では“報告より現場対応”が優先されるため、問題が起きてもその場で修正してしまい、日本側には知らされないまま遅れが積み重なっていくことがあるのです。
工期が読めない理由は「人材の流動性」にあり
台湾の職人文化は非常に流動的です。
多くの職人が固定の会社に所属せず、「請負(バイト)単位」で現場を渡り歩くのが一般的です。
そのため、職人が別現場の都合で抜けたり、急な家庭事情で休むと、代わりの人材を探すまで作業が止まるという事態が頻発します。
さらに、台湾の祝祭日や天候も工期に大きな影響を与えます。
旧正月や中秋節などの連休期間中は、多くの職人が故郷へ帰省し、1〜2週間ほど現場が完全にストップすることもあります。
このような社会的・文化的背景を理解せず、日本の「厳密な日程管理」を前提にスケジュールを組むと、確実にずれが生じます。
したがって、台湾での工程計画では、「予備日を1〜2週間設ける」ことを前提にするのが現実的です。
「OKです!」が“まだ始まっていない”合図のことも
台湾の現場関係者は、打ち合わせ時にとてもフレンドリーで、前向きな返答をします。
「OKです!」「沒問題!(問題ない)」という言葉を聞くと、日本人は“もう準備ができている”と解釈しがちです。
しかし実際には、「理解しました」「考えておきます」のような曖昧な同意であることも多いのです。
つまり、“言葉のOK”と“実行のOK”が一致していないのです。
たとえば、図面承認を求めた際に「OK」と言われても、実際には上司やオーナーの確認が済んでおらず、作業が進められないケースがよくあります。
このギャップを埋めるには、「いつまでに何をするのか」を書面で確認することが欠かせません。
口頭合意ではなく、スケジュール表・メッセージ履歴・承認サインなど、記録が残る形で進行管理を行うことが、台湾では特に重要です。
日本式の進捗管理を台湾に導入する際の注意点
日本企業が台湾でプロジェクトを進める際、「日本式の工程表」をそのまま使うことは難しいです。
台湾の職人や協力会社は、「細かすぎる指示表」には慣れていないため、1日単位の進捗表を渡しても、実際には“誰も見ていない”ということがよくあります。
そのため、工程表は「週単位」「大項目レベル」で伝えるほうが効果的です。
たとえば「10月第2週:壁仕上げ完了」程度にまとめると、現場側も理解しやすくなります。
また、各工程の担当者を明確に記載することで、「誰が責任を持つのか」が可視化されます。
さらに、定期的に現場ミーティングを設けることが非常に有効です。
台湾では、書類よりも“対面で話す”ことが重視されます。
短時間でも週1回の現場打合せを設定することで、遅延の兆候を早期に発見できます。
納期を守るために設計者ができる3つの予防策
スケジュールを守るためには、設計者自身の関与が欠かせません。
「図面を渡したら終わり」ではなく、「現場が動き出すまで」責任を持つことが求められます。
その上で、次の3つの予防策を実践することで、納期遅延を最小限に抑えることができます。
① 着工前の「現場スタート確認」を徹底する
台湾では、図面承認後も実際に工事が始まるまでタイムラグが生じることがあります。資材発注、職人手配、オーナー決裁──どれか一つでも止まれば全体が止まります。したがって、「誰が、いつ、何を始めるのか」を着工前に再確認することが重要です。
② 工事期間中の「中間チェック日」を設定する
台湾では進捗報告が形式化しづらいため、設計者が「中間確認日」をカレンダーに明記しておくとよいでしょう。“この日にここまで終わっていなければ遅れている”という基準を共有することで、現場の意識が変わります。
③ 「オープン日から逆算」ではなく「現場実態から積み上げ」る
日本では開業日を先に決めて工程を組みますが、台湾ではそれがリスク要因になります。むしろ、現場状況と職人の可動性を見ながら、現実的な工期を設計者が主導して提案するほうが、結果的にスムーズに進行します。
これらの工夫により、日本式の管理と台湾式の柔軟性を両立させたスケジュール運営が可能になります。
第4章:法規・検査・消防──“知らなかった”が命取りになる
台湾での店舗設計・内装工事において、日本企業が最も見落としやすく、かつ最も深刻なトラブルにつながるのが「法規・検査・消防」の問題です。
- 「日本で問題なかった設備が台湾ではNGだった」
- 「工事は終わったのに、営業許可が下りない」
こうした事例は後を絶ちません。
日本では、設計段階で行政確認を取りながら進めるのが一般的ですが、台湾では制度と運用が地域ごとに異なり、 “誰がどこまで責任を持つのか”が非常に曖昧なことが多いのです。
しかも、消防・建築・営業の3つの許可がそれぞれ別ルートで審査され、どれか1つでも通らなければ店舗がオープンできません。
図面承認の遅れがすべてを狂わせる
台湾では、建築・消防・商業許可など、さまざまな行政機関への申請が必要ですが、申請フローが自治体によって大きく異なります。
同じ「台北市内」であっても、区によって担当部署や審査期間が違うこともあり、その調整に時間がかかるのが現実です。
特に問題となるのが、図面承認の遅れです。
日本企業の多くは「工事図面が完成した段階で申請に出す」と考えますが、台湾では「建築技師(Licensed Architect)」が署名・押印した図面でなければ受理されません。
この建築技師の手配に時間がかかることが多く、結果として着工が遅れるケースが後を絶ちません。
さらに、建築技師は“設計者とは別”であり、外部委託が一般的です。
つまり、設計が完成しても、技師が承認印を押さなければ申請は進みません。
そのため、早い段階から技師をアサインしておくことが、スケジュール遅延を防ぐ第一歩です。
消防検査に落ちる“よくあるデザイン要素”
台湾の消防検査(消防安全檢查)は非常に厳格で、デザイン重視の日本企業ほど落としやすいという傾向があります。
よくある例としては、
- 天井裏に設けた照明ダクトや装飾がスプリンクラーの噴射範囲を妨げている
- 非常灯や出口サインをデザイン的に隠してしまった
- カウンターまわりの電気設備が防火規定に適合していない
などです。
特に注意すべきは、台湾では消防法規が「実際の施工状態」で判断される点です。
図面上でクリアしていても、現場でわずかに配置がずれただけで不合格になることがあります。
また、消防検査官の裁量が大きいため、同じ仕様でも検査官によって判断が異なるというケースもあります。
このリスクを避けるためには、設計段階から「消防設備業者」と協働し、「検査に通るデザイン」を共に検討する姿勢が重要です。
台湾の「建築技師」制度を理解しないと危険
日本の設計者が誤解しやすいポイントのひとつに、台湾の「建築技師」制度があります。
台湾では、建物の用途変更、増改築、商業施設の内装などを行う際に、必ず“有資格の建築技師(Architect)”が法的責任者として関与しなければなりません。
この建築技師は、設計者のようにデザインを行うのではなく、法規・構造・安全面の審査に責任を負う存在です。
つまり、図面を描くのは設計会社、申請の責任を負うのは建築技師という二重構造になっています。
ここで問題となるのが、建築技師が設計内容を理解していない場合、安全面の理由からデザインを大きく修正するよう求めてくることです。
「柱を増やしてほしい」「天井を下げて配管を隠すのは危険」など、意匠的な発想と相反する指摘が入ることも少なくありません。
そのため、日本企業は設計初期段階から建築技師を巻き込み、「デザイン意図を理解した上で合法的に成立させる」仕組みを整える必要があります。
日本ではOKでも台湾ではNGな素材・設備例
日本の店舗で一般的に使用されている素材や設備の中には、台湾では法的に使用できないものが数多くあります。
たとえば、
- 日本の防火区画基準を満たす塗料でも、台湾の消防認証が取れていない
- 日本製の電気機器が台湾の検査機関(BSMI)登録を受けていない
- 店舗サインの照明電圧が規定を超えている
などのケースです。
また、厨房設備においても、ガス配管や換気ダクトの設置基準が日本とは大きく異なります。
「厨房内の火源から防火壁までの距離」「排気口の高さ」「消火設備の位置」などが厳密に定められています。
これを知らずに施工すると、消防検査に落ちるだけでなく、再施工費用が発生することになります。
つまり、台湾での内装設計においては、日本製=安全・合法という認識は通用しません。
現地の法規データベースを確認するか、台湾側の設計会社・設備業者に事前相談することが不可欠です。
法規リスクを避けるための設計段階でのチェック体制
台湾での設計・施工を安全に進めるためには、法規チェックを「事後」ではなく「事前」に行う仕組みを構築することが必要です。
その具体的なポイントは、次の3つです。
① 設計初期に行政条件を確認する
台湾では、建物の用途変更や区分登記によって、同じビルでも使用可能な業種が異なります。設計を進める前に、ビルオーナーと行政の双方に確認を取ることが必須です。
② 建築技師・消防業者・電気設備業者の三者協議を行う
設計段階でこれらの専門家を交えた打合せを行うことで、後から「法規に合わない」と言われるリスクを大幅に減らすことができます。
③ 行政検査のスケジュールを工期に組み込む
申請から検査完了までには数週間〜1ヶ月かかるのが一般的です。日本式に「完工→即オープン」とはいかないため、検査期間を含めたスケジュール設計が不可欠です。
台湾では、「知らなかった」では済まされないのが法規です。
たとえ図面や施工が完璧でも、法的認可が下りなければ店舗は営業できません。
日本企業が現地で信頼されるためには、この“見えない工程”を理解し、現場と行政の間に立って調整できる存在になることが求められます。
第5章:コミュニケーションの断絶──伝えたつもり、伝わっていない
台湾で店舗設計や内装工事を進める際、日本企業が最も苦戦するのが「伝達のズレ」です。
図面、メール、打ち合わせ、LINE──いくら丁寧に説明しても、思ったように伝わらない。
- 「ちゃんと伝えたはずなのに」
- 「確認したのに違う仕上がりになった」
そんな声を、私はこれまで何度も耳にしてきました。
この“伝わらない”という現象は、単なる言語の壁ではありません。
背後には、日本と台湾のビジネス文化・コミュニケーション習慣・責任意識の違いがあります。
特に、設計・施工といった多職種が関わる現場では、この違いが顕著に現れます。
「伝わらない理由」は言語よりも“ニュアンス”にある
日本企業の担当者が「通訳を介して打ち合わせをしたから安心」と思っても、実際には内容が意図通りに伝わっていないことが多くあります。
その最大の理由は、“ニュアンス”の違いです。
日本語の「できれば」「検討してください」「もう少し落ち着いた色で」という表現は、実は非常に曖昧で、台湾語や中国語では具体的に解釈できない場合があります。
たとえば、「もう少し落ち着いた色で」と伝えた場合、日本人なら“トーンを下げる”と理解しますが、台湾人デザイナーは“派手さを抑える”と捉えるかもしれません。
このように、同じ言葉でも文化的背景が違うと、受け取り方もまるで変わってしまうのです。
そのため、台湾での打ち合わせでは、「言葉よりも具体例」が重要です。
写真・カラーチップ・スケッチなど、視覚情報を用いて“何を求めているのか”を明確にすることで、誤解を最小限に抑えることができます。
台湾の現場で通じる「確認」の言い方
台湾では、日本のような「逐一確認」「細かく指示する」という文化があまり浸透していません。
そのため、「これで大丈夫ですか?」と聞いても、「OKです」と答えることがほとんどです。
しかしその“OK”が本当に理解を示しているのか、確認する必要があります。
私が現場で実践している方法は、「Yes/No」ではなく「説明させる確認」です。
つまり、「どう施工する予定ですか?」「どんな仕上がりになりますか?」と、相手の口から説明してもらう形で理解度を確認するのです。
台湾の職人はプライドが高く、質問されると一生懸命答えてくれます。
このやり取りを通して初めて、「どこまで理解しているのか」「どこが誤解されているのか」が見えてきます。
また、確認の際には「質問は悪いことではない」という雰囲気を作ることが重要です。
台湾では、上司や発注者に質問することを“失礼”と感じる人も多いため、「確認してくれてありがとう」と声をかけることで、コミュニケーションの質が一気に向上します。
メール文化よりも「LINE報告」が主流な理由
日本では、進捗報告や確認事項をメールでやり取りするのが一般的ですが、台湾ではLINE(あるいはWeChat)による報告が主流です。
工事現場の職人や監督、設計担当も含め、現場の連絡はほとんどリアルタイムのメッセージで行われます。
この文化の背景には、「スピード重視」「即時対応」の台湾的ワークスタイルがあります。
日本式の長文メールでは対応が遅れ、既に現場が動いてしまうことも多いのです。
そのため、台湾で設計・施工を進める際は、LINEグループを活用した情報共有を導入すると効果的です。
現場写真の共有、日々の進捗、変更指示の確認などをグループ内で行えば、記録も残り、スピーディな対応が可能になります。
最終的な合意や設計変更は、必ずPDFなどの文書で残すようにしましょう。
「口頭で伝えた」「チャットで言った」では、後々トラブルの原因になります。
「指示書」よりも「現場立会い」が重要なわけ
日本では、図面や指示書を整備すれば現場が動くという前提があります。
しかし台湾では、書面より“現場での対話”が最も重視されるのです。
これは、台湾の現場文化が“人間関係ベース”で成り立っているからです。
職人たちは、紙の指示よりも「誰が言ったか」を重視します。
設計者が直接現場に顔を出し、「この部分はこうしてほしい」と伝えるだけで、図面よりも正確に意図が伝わることがよくあります。
また、台湾の職人は「信頼できる相手のために頑張る」という意識が強いため、現場に足を運ぶ頻度が多いほど、仕上がりの品質が向上します。
反対に、現場を訪れず、指示書だけを送って済ませると、「本気で見てくれていない」と受け取られ、施工精度が落ちることさえあります。
したがって、台湾では“指示書文化”よりも“対話文化”が有効です。
設計者が現場に立ち会い、目で見て、手で示して伝える ── これが最も確実な方法です。
設計者が信頼を得るための“人間的距離感”とは
台湾の現場で成功している日本人設計者には、ある共通点があります。
それは、「技術よりも人間関係を大切にしている」ということです。
台湾では、契約や図面よりも「信頼関係」が最優先されます。
一度「この人は誠実だ」と思われれば、多少のトラブルがあっても柔軟に対応してもらえます。
逆に、「冷たい」「上から目線」と見なされると、協力関係が崩れ、どんなに正しい指示をしても動いてもらえなくなります。
信頼を築くためには、まず相手の文化を尊重する姿勢を見せることが大切です。
たとえば、打ち合わせ後に「今天也辛苦了(今日もお疲れさま)」と声をかけたり、小さな差し入れをするだけでも、現場の雰囲気は劇的に変わります。
また、「叱る前に感謝を伝える」ことも効果的です。
台湾の職人はプライドが高く、頭ごなしの注意を嫌います。
「ここは少し違っていたけど、昨日の作業はとても丁寧だった」と前置きしてから指摘すると、その後の対応が驚くほどスムーズになります。
最終的に、台湾で信頼される設計者とは、図面の正確さだけでなく、“人を動かすコミュニケーション力”を持つ人なのです。
まとめ:台湾の現場に“通じる設計者”になるために
台湾での店舗設計・内装工事において、日本企業が直面する設計ミスの多くは、実は「技術不足」ではなく「理解の不足」から生まれています。
第1章から第5章までを通じて見えてきたのは、日本と台湾では“正しさ”の基準が違うという現実です。
日本の設計は「正確さ」「整合性」「再現性」を重んじ、図面どおりの完成を理想とします。
一方、台湾では「柔軟さ」「即応力」「結果重視」が価値とされ、現場での判断が尊重されます。
どちらが優れているという話ではなく、求められる方向性が根本的に違うのです。
1. 図面よりも「理解」が重要
第1章で触れたように、台湾では図面の細かさよりも「現場でどう伝えるか」が重視されます。
完璧な図面を描いても、それが読み取られなければ意味を持ちません。
むしろ、“どの部分を絶対に守ってほしいのか”を共有し、現場との理解を合わせることが成功の鍵です。
つまり、設計者は「図面を描く人」ではなく、「意図を翻訳する人」でなければならないのです。
2. 素材と仕上がりは“文化と環境”で変わる
第2章では、素材や施工精度の違いから生まれる“仕上がりのズレ”を取り上げました。
湿度・気温・職人の経験値・流通材の違い ── これらが複雑に絡み合い、同じ設計でも日本とは異なる結果をもたらします。
ここで大切なのは、「台湾では台湾の美しさを見つける」という視点です。
日本式の完成度を押しつけるのではなく、現地の素材感や施工感覚の中に“魅力”を見出すことで、本当の意味で“台湾らしい日本デザイン”が生まれます。
3. スケジュールは「約束」ではなく「共通目標」
第3章では、スケジュール感覚の違いを見てきました。
台湾では、「工程表=目安」であり、「遅れ=失敗」ではありません。
この感覚の違いを理解せず、日本式の厳密な日程を押し付けると、関係がぎくしゃくします。
解決策は、“管理する”から“伴走する”へ発想を変えること。
進捗を責めるのではなく、現場と一緒に「どうすれば間に合うか」を考える姿勢を見せると、台湾のパートナーは信頼と尊敬を返してくれます。
4. 法規を知らずして、設計は完成しない
第4章では、台湾特有の法規・消防・検査の仕組みを解説しました。
ここは「知らなかった」では済まない領域です。
いくら良いデザインでも、消防検査に通らなければ店は開けません。
設計初期の段階から、建築技師・消防業者・行政との連携を組み込み、“法規に強い設計体制”を整えることが、台湾出店成功の前提条件です。
5. 言葉よりも「関係」がすべてを動かす
そして第5章で明らかになったのは、最も根本的な問題 ―― コミュニケーションの断絶です。
台湾の現場では、メールよりLINE、指示書より立会い、言葉より表情が重視されます。
つまり、人間関係の温度が、施工品質を左右するのです。
「伝える」ではなく「伝わる」。
そのためには、相手の文化を尊重し、共に現場で汗をかく姿勢を見せることが何よりの信頼構築です。
図面よりも、人との信頼が現場を動かします。
最後に ── “日本品質”を台湾で実現するために
台湾の店舗設計・内装工事で成功する日本企業に共通しているのは、「日本式を押し通す」のではなく、「台湾式を理解したうえで日本式を応用している」点です。
つまり、日本品質 × 台湾の柔軟性 = 現地で愛される空間。
その掛け算を成立させることこそ、真の国際設計力といえます。
台湾の現場は、決して日本式を拒んでいるわけではありません。
むしろ、「丁寧で誠実な日本のやり方」を尊敬し、それを吸収したいと考えています。
その思いに応えるためには、まず日本側が台湾文化を理解し、“共に創る”姿勢を示すことが何より大切です。
終わりに
台湾の店舗設計・内装工事には、数多くの違いと難しさがあります。
しかしその一方で、日本企業にとって学びの宝庫でもあります。
違いを知り、誤解を超え、信頼を築く。
それこそが、海外展開で本当に価値ある「現場力」を磨くことにつながるのです。
“通じない図面”を嘆くのではなく、“通じる人間関係”を育てる。
その先に、日本と台湾が共に成長する、新しい空間づくりの未来があります。